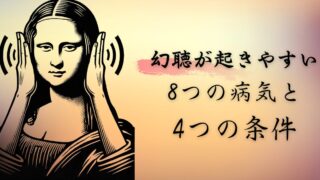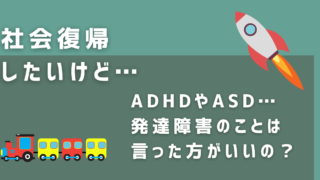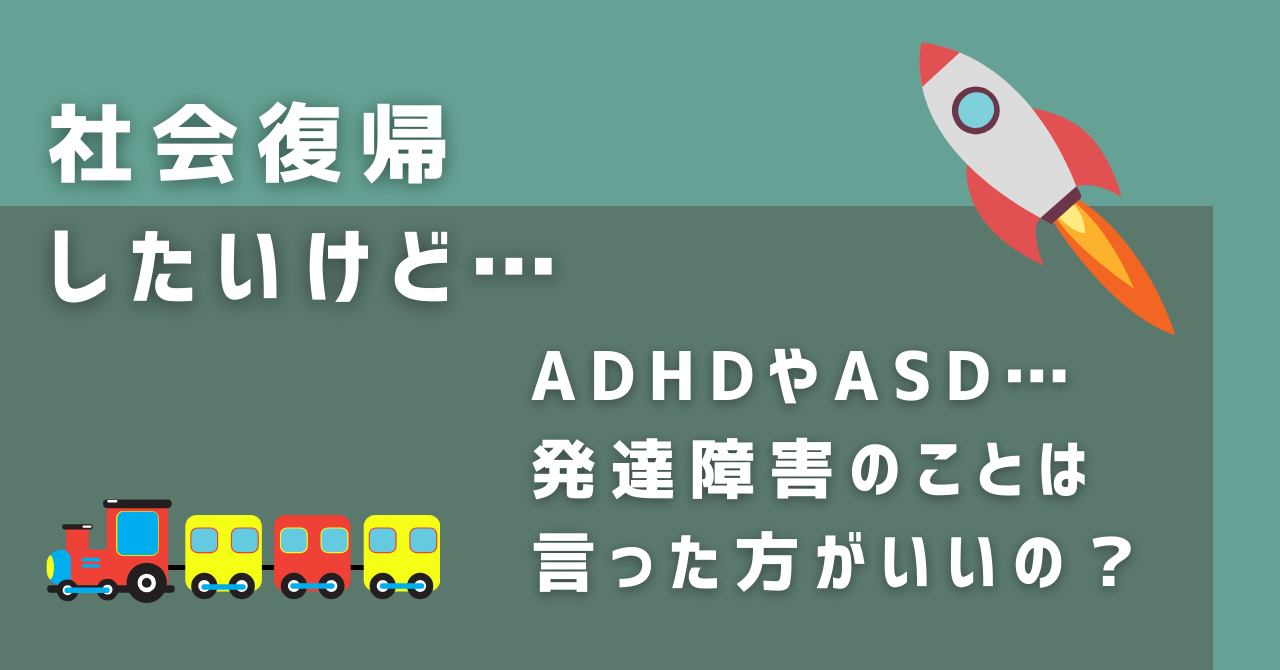社会復帰を考えている方の中には、ADHDやASDなどの発達障害が背景にあり、そこから生じる二次障害(うつ病や不安障害など)によって休職していた方も少なくありません。
そうした方が復職を検討するとき、「障害者雇用(いわゆる『障害者枠』)で新たに転職するべきか」「元の職場に戻り、自分の障害をオープンにするか、あるいは隠したままで続けるか」で悩むことがあります。
ここでは、それぞれの選択肢のメリットと気をつけたい点を整理してみました。ご本人はもちろん、ご家族がいっしょに考える際の参考になれば幸いです。
1. 障害者雇用(障害者枠)で新しい職場へ転職する場合
メリット
- 配慮を受けやすい
- 会社側が、障害を持つ方の特性を理解して受け入れる体制をあらかじめ整えていることが増えてきました。
- 就業時間や仕事内容、休憩の取り方などについて相談しやすく、無理なく働くための調整が期待できます。
- 正直に伝えやすい環境
- 「理解してもらえないのでは」という不安が少なくなるため、必要なサポートを受け取りやすくなります。
- 周囲のスタッフや上司も、発達障害の特性に合った関わり方を心得ているケースが多いです。
- 公的支援や専門機関のサポートが受けやすい
- 障害者雇用に力を入れている企業は、関連の支援サービス(ジョブコーチや就労移行支援など)と連携している場合があります。
- 仕事のスキルだけでなく、生活リズムやストレスケアなど、総合的な支援を受けられる可能性があります。
気をつけたい点
- 給与やキャリア面で制限がある場合がある
- 一般枠と比べてスタート時の給与やポジションが低く設定されるケースがあります。
- その会社の制度や方針にもよりますが、収入面を優先したい方にとってはデメリットになることがあります。
- 周囲の理解度は職場によって異なる
- 「障害者枠」という形だけは整っていても、実際のサポート体制が不十分な企業もあります。
- 入社前に見学や面談を行い、働くうえでどの程度の配慮があるか確認したほうが安心です。
- 障害をオープンにして働く不安
- 「障害を開示しているから、他の社員とは違う扱いを受けるのでは?」という心配があるかもしれません。
- しかし、無理に隠して体調を崩すよりは、配慮を得られるほうが長期的には安全な場合もあります。
2. 元の職場に戻る(障害をオープンにする・しない)
メリット(オープンにする場合)
- 環境や人間関係をある程度知っている
- ゼロからのスタートではないので、新しい職場に比べると慣れる負担が軽い場合があります。
- 仕事内容を把握していることで、特性に合った工夫(たとえばマルチタスクを減らす、コミュニケーションルールを作るなど)が考えやすいです。
- 会社のサポートや理解が得られる可能性
- もし会社側があなたの状況を受け止めてくれるなら、障害の特性に合わせて配置転換や働き方の調整をしてくれるかもしれません。
- 休職前の実績を評価してくれている場合、復職後も同等の待遇が維持されることがあります。
気をつけたい点(オープンにする場合)
- 職場全体の理解がどこまで広がるか
- 一部の上司や人事担当者が理解していても、現場の同僚が必ずしも同じレベルの理解を持っているとは限りません。
- 周囲の偏見や無理解に傷つく可能性もあります。
- 障害に対する評価や期待の変化
- 障害があると知られたことで、「これまでと同じようには仕事を任せられない」と判断される場合があります。
- 必要な配慮を受けやすくなる一方で、「できること」や「やりたいこと」を過度に制限される可能性も。
メリット(隠して復職する場合)
- 今までの評価や役割を維持しやすい
- 障害の話が表に出なければ、周りから特別な目で見られることは少なくなります。
- 復帰後も、以前と同じ立ち位置で働ける場合があります。
- プライベートな情報を守れる
- 障害の開示に抵抗がある場合、自分のタイミングで話すかどうかを選べます。
- 周囲から「特別扱いされるのでは」という不安が減ります。
気をつけたい点(隠して復職する場合)
- 配慮やサポートを得にくい
- 障害があることを伝えなければ、会社や同僚は適切な対応をとれません。
- 結果的に、体調を崩す原因が解決されないまま仕事を続けることになり、再休職のリスクが高まる場合があります。
- 自分で無理を抱え込みやすい
- 特性に合わない業務やコミュニケーションを求められても断りにくく、ストレスが蓄積しやすいです。
- 症状が悪化してしまうと、再び休まざるを得なくなるかもしれません。
3. 判断のポイント

- 現在の体調・特性の程度
- 今の状況で、どの程度の配慮があれば安定して働けるのかを確認することが大切です。
- 医師やカウンセラー、就労支援機関の担当者と相談して、必要なサポートを明確にしましょう。
- 職場の理解や制度の有無
- 元の職場がどこまでサポートしてくれるのか、相談する環境はあるのかをリサーチする必要があります。
- 可能なら、上司や人事担当と面談して話し合いの場を持つことで、復帰後の具体的なイメージがわきやすくなります。
- 長期的な働き方の見通し
- 一時的に給与が下がっても、無理なく働き続けられる職場を選んだほうが、結果として安定したキャリアになる場合があります。※雇う側は休職や復職・転職を短期間で繰り返している方よりも「障害の有無よりも長く勤められる人かどうか」を重視して雇用することが多いため
- 短期的な条件よりも、「続けやすさ」「自分の特性に合った職場かどうか」を重視すると、再休職のリスクを減らせます。
- 家族や専門家のサポートを活用する
- 本人やご家族だけで抱え込まず、発達障害に詳しい支援機関やカウンセラー、ジョブコーチなどに相談するのも一手です。
- 障害者枠の求人情報はハローワークや専門エージェントで探せるので、情報収集を積極的に行いましょう。
おわりに
ADHDやASDなどの特性が理由で休職していた方が復職を考えるときには、障害をオープンにするかどうかを含めて、多くの迷いや不安を抱えるものです。
実際には「これが絶対に正解」という答えはなく、ご自身の状況や希望、そして会社や転職先の受け入れ体制によって合う選択肢が変わってきます。
大切なのは、ご本人が安心して働ける環境を確保すること。
再び休職しないためにも、必要なサポートや配慮をきちんと受けられるかを考えることが重要です。
ご家族も、焦らず、まずは専門家や支援機関の知恵を借りながら、一緒に取り組んでいけるといいですね。
自分の特性や体調に合った方法で働くための情報や選択肢は、思っている以上にたくさんあります。
どうぞ遠慮なく、周りの人や専門機関にサポートを求めてみてくださいね!
障害者手帳の種類と取得
日本でいわゆる「障害者雇用枠」に応募する場合、基本的には何らかの障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)の所持が求められます。
- 身体障害者手帳 … 身体機能の障害がある場合
- 精神障害者保健福祉手帳 … うつ病・統合失調症・ADHD・ASDなど精神疾患・発達障害の診断があり、一定の条件を満たす場合
- 療育手帳 … 知的障害がある場合
これらの手帳を持っていることで、法的に「障害者」として認められ、企業が法律に基づいて雇用する「障害者雇用枠」に該当しやすくなります。
ただし、企業によっては独自の雇用制度を設け、手帳がない場合でも配慮をして採用するケースがゼロではありません。
ADHDやASDの場合は?
ADHDやASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害は、「精神障害者保健福祉手帳」の対象になることがあります。
- 医療機関で正式な診断を受け、一定の基準を満たせば、手帳を取得できる可能性があります。
- 取得することで、障害者雇用枠への応募や、就労支援サービス(ジョブコーチなど)が利用しやすくなります。
手帳を取得するときの注意点
- 申請に時間がかかる:診断書や各種書類を準備し、自治体に申請してから交付までに数か月かかることもあります。
- 等級によってサポート内容が変わる:特に精神障害者保健福祉手帳は、障害の重さなどによって等級が決まり、受けられる支援やサービスが変わります。
手帳の取得を迷うとき
- 「手帳を取得して、障害をオープンにすることのメリット・デメリット」は人によって異なります。
- 取得することで職場の配慮が得やすくなったり、公的支援を利用しやすくなる一方、「障害者として扱われること」に抵抗を感じる方もいます。
- 就労支援機関やカウンセラー、医師に相談しながら、自分の働き方や体調に合った選択を考えるとよいでしょう。
まとめ
- 原則として、障害者雇用枠への応募には障害者手帳が必要です。
- ADHDやASDの場合は、精神障害者保健福祉手帳を取得するケースが多いです。
- 手帳を持っていると企業や行政からサポートを受けやすくなる一方、手帳取得に対する抵抗感や開示の悩みもあるでしょう。
- 就労継続のためにも、医師や専門家、家族と話し合いながら、手帳の取得や働き方について検討してみてください。