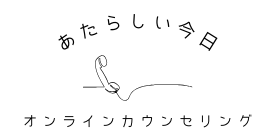子どもに情緒的に関心を向けることができなかった祖母に育てられた母は、その反動で「過関心」をわが子に向けるようになり、それを嫌がる私たち姉弟を「過干渉」に、真ん中の弟を支配下におき「洗脳」しました。
過関心→過干渉→虐待→支配→洗脳

弟2人が酷い目に遭わないようにスケープゴートになっていた私の体には、今も無数の傷や痕が残っています。
父は幼い頃の私たち姉弟を可愛がってくれました。しかし母の育児が常軌を逸する過干渉になり、それがもとで私と言い争うようになってくると、家族のために建設的に話し合うことも、子どもを守るために離婚という選択をとることもせず、暴力的・威圧的に母を止めようとするか、
私に「お母さんを刺激するな」「それなりに、適当に『はい』と言っておけばいいんだから」と愚にもつかないアドバイスをするようになりました。
それでも授業参観や懇談会に来てくれたり、進路相談にのってくれたり「母よりは話ができる」「母よりは笑って話ができる」というだけで、子どもの頃の私たちは父を家人・家長として優れていると勘違いし、父を好きで父を頼っていました。
毒親育ちの成人式は曇天に

大学進学と同時に家を出て2年が過ぎ、成人式に出るべく実家のある駅に降り立つと、新幹線の車窓の奥に広がっていたはずの高く青い空が曇天に見えました。
本当に曇ってしまったのか、それとも私の心模様が反映されたのか今や記憶にもありませんが、私の帰省を喜び目を細める父に対して母は、娘の成人をどのように受けとめればいいのか戸惑っているようで、お祝いの言葉ひとつかけられたおぼえがありません。
しかし、“それなりのご馳走”をつくり、片付けられない母が玄関やリビングを片付けた状態で迎えてくれたことから、母なりに「祝う気持ち」「帰省を迎える気持ち」はあったのだろうと思います。
でもこの帰省を最後に、私はしばらくのあいだ実家と没交渉になります。2年間、実家と離れて暮らしたからこそ「ここに私の居場所はない」「ここに私は居たくない」――自分の本当の気持ちがはっきりとわかりました。
「家を捨てて、親を捨てて、自分のために生きよう」
一点の曇りなく迷いなくこう思えたのは、上京して一人暮らしをしたからに他なりません。私は良い選択をしたと今も思います。
毒親育ちが20代に思っていたこと

- 一家団欒がしんどい
- 父と母が揃うと疲れる
- 実家にいると生気を吸い取られる
- 実家にいると自己肯定感を吸い取られる
- もうじゅうぶん頑張ってきた
- もうじゅうぶん戦って踏ん張ってきた
- だからもう、親の求める子どもの役割を終えよう
- 「子ども」なんて要らない
- 「家族」を持つイメージが湧かない
- 虐待が「繰り返されること」が怖い
- 私も虐待母になってしまうかもしれないという怖さ
上京という形で親元を2年離れたからこそ見えてきたものや、私自身の本心に気づけました。
私にとって実家はひとつ屋根の下で親子が仲良く暮らす場所ではなく、生きるか死ぬか、自尊心を奪われるか守るかの戦場。母の機嫌で戦火は燃え広がり、力づくでそれを抑えつけようとする父と言い争う声に耳を塞ぎ
「出ていきたい…出ていきたい…死んでほしい、消えてほしい」
と毎日のように思ってたあの頃は、家を出れば幸せが待っているなんて予想もしませんでした。ただただ、家を出たい。この家を出られるなら、親を捨てられるなら、どんなつらいことにも耐えてみせる――。
家さえ出られるならどんなつらいことも耐えれられる

「この家を出られるなら、親を捨てられるなら、どんなつらいことにも耐えてみせる――」だから家や親と離れさせてほしいと心から願っていました。
けれど実際には「小さな幸せ」がいくつも目の前に落ちていました。
今思えばそれはとくべつに幸せなんかじゃなく「得られる当たり前の権利」「得ても許される当たり前の日常」なんだけど、それさえもこの上ない幸せに思えるほどの地獄を18年間も味わっていたんだな、よく頑張ってきたなと、やっと自分を褒めることができました。
毒親育ちの私の20代はこんな日々でした。次回、毒親育ちが30歳になって思ったことに続きます。