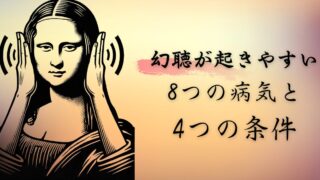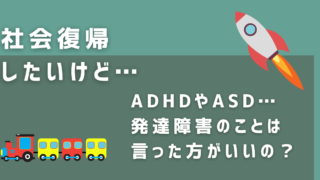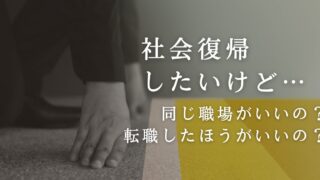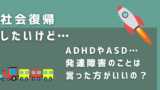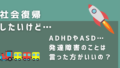『診断書』と聞くと、職場に休職などを申し入れるために提出するものだとお思いのかたが多いかもしれませんが、復職のハードルを下げ「自分らしくムリなく働けるように」診断書を書いてもらうこともできます。
お勤め先によっては復職診断書を必要としないこともありますが、休業明けの社会復帰って多くの人にとっては緊張や不安を伴いますので、私は復職のための診断書は提出したほうが良いと考えています。
「そろそろ職場復帰を考えたいんですけれど、主治医の許可や産業医の意見書が必要なんですよね…」
そうおっしゃる患者さんと向き合うとき、私はいつも、「ただの“許可証”としての診断書にしない」ことを意識しています。
休職のきっかけは、人それぞれです。
過重労働だったのかもしれないし、対人関係のストレスが大きかったのかもしれない。発達障害の特性と働き方が合わなかったのかもしれません。あるいは、勤務形態が自分の体調に合わなかったのかもしれません。
いずれにせよ休養が必要だったほどの状態であれば、復職に向けて何らかの配慮や調整が必要なはずです。その調整内容を文書で示すのが、「復職用の診断書」。
単に「働けるようになりました」という一文だけでは、患者さんの再発リスクを減らすには不十分です。
ですから私は、なるべく具体的な提案を書き込むようにしています。
たとえば、
- 「最初の1か月は短時間勤務にして、朝晩の通勤ラッシュを避けやすいよう配慮を」
- 「月1~2回のカウンセリングや通院を継続できるよう、定期的な休暇やスケジュール調整が望ましい」
- 「本人が苦手なマルチタスクはなるべく分割し、業務の優先順位を上司と確認しながら進める」
といった具合です。
すると、患者さんは「先生がこう書いてくださったから、会社に伝えやすくなった」と安心されることが多いですね。
会社にとっても、「何をどう配慮したらよいのか」を専門家の立場から示されることで、動きやすくなる側面があります。もちろん、すべてがスムーズにいくわけではないのですが、少なくとも口頭で言うだけよりは、理解してもらいやすいはずです。
また、診断書を書くときに大事なのは、患者さんご自身とよく対話すること。
「どんな働き方が、あなたにとって無理なく続けられそうですか?」
「職場で困りそうなことは何ですか? どうすればその不安が少なくなると思いますか?」
――こんな質問を投げかけると、患者さんも自分の心と向き合うきっかけになります。
なかには、「そんなことをお願いするなんて申し訳ない」と遠慮する方もいらっしゃいます。
でも、実はそうした相談こそ、私たちが日々望んでいることなんです。
主治医や担当カウンセラーが状況を正しく把握し、適切なアドバイスを示せるようになるほど、患者さんが安心して働ける環境づくりに近づいていきます。
診断書は、ただの証明書ではなく、「専門家からの具体的な提案」を形にできるツールです。
もしあなたが休職中で、復職を考えているならば、ぜひ遠慮なく主治医や担当カウンセラー・公認心理士に相談してみてください。
「どんな働き方なら再発しにくいか、一緒に考えてほしいんです」
そんなひと言から、あなたが戻る職場の環境が大きく変わるかもしれません。
私が書く診断書のたたきは、患者さん自身へのメッセージでもあります。
「焦らず、無理をしないでほしい」「もう少しサポートを受けながらなら、きっと大丈夫」と伝えたいからこそ、できるだけ具体的に記載するのです。
それを患者さんが会社に示したとき、上司や同僚も「何をサポートすればいいのか」がはっきりわかります。
復職までの道のりには、不安がつきものです。
でも、医師が書く診断書は、その不安を減らすための一つの手助けになります。
ぜひ、頼ってください。あなたが再び笑顔で働けるように、そして同じ苦しみを繰り返さないように――主治医と連携しながら、一緒に乗り越えていきましょう。
私はオンラインカウンセリングも行っています。
オンラインではあなたの主治医にはなれませんが、あなたの主治医宛てに「こういった診断書の作成をお願いします」とご提案差し上げることなら可能です。※主治医に失礼のないよう最大限の配慮を致しますのでご安心ください
医師が診断書を書くことも、診断書の依頼書やたたきをつくることも「有料」です。笑
ですので誰に遠慮なさることなく堂々と「依頼なさって」ください。自分らしくのびのびと働けるって、とっても素敵なことですから✨