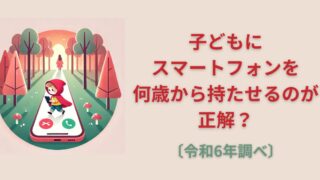子どもは5歳くらいから「ウソ」を吐き始めると言われていますが、喜ばしい成長の証ですね。
親やおじいちゃんおばあちゃんを、喜ばせたり驚かせたいというサービス精神。関心を集めたい・話を聞いてほしいという自己欲求。時にはいたずらを叱られたくなくて自己保身からついてしまうウソもありますが、それも健全な成長の証拠と言えるでしょう。
今回は思春期――中学生~大学生まで――の子どもたちが、事実に上乗せして話を盛ったり、真実7割に対してウソを3割混ぜて物事を伝えてしまう心理的背景について書きたいと思います。
思春期特有の心の動き
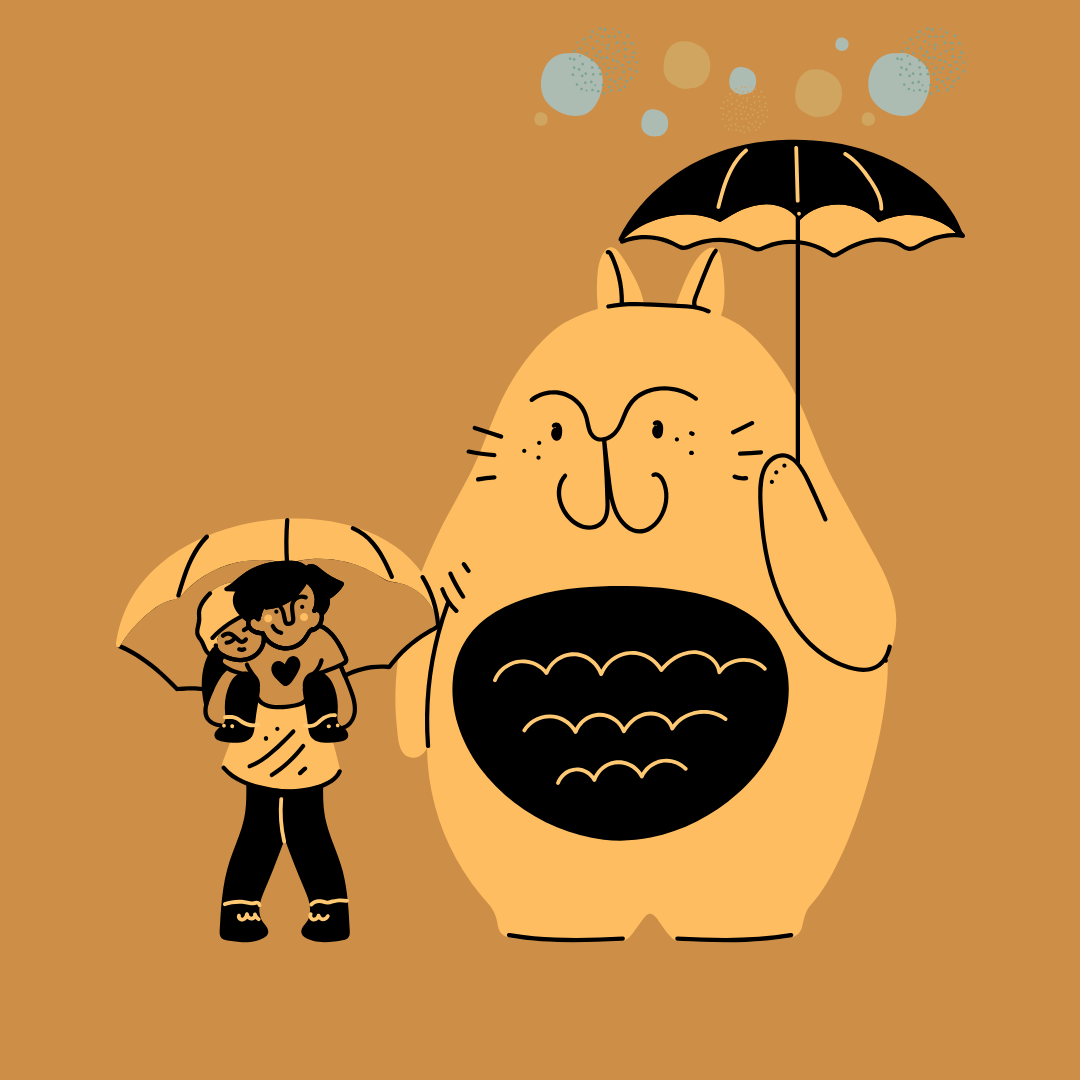
自己肯定感や自己イメージの揺れ
思春期は「自分って何者なんだろう?」と模索する時期です。
自己評価が安定せず、周囲にどのように認められ受けとめられているかを“強く”気にする傾向が高まります。ライバルと自分を比較して落ち込んだり、威張ってみたりと感情が常に揺れていて忙しい。
少し話を盛ることで自分の存在感を示したり、「おもしろい!」「すごい!」などと肯定的に見られたい気持ちを満たします。
仲間とのつながりや共感を求める気持ち
同年代の仲間とのつながりが優先される時期でもあります。
周囲から「すごいね!」と言われたり、共感を得られたりすることで安心感や一体感・『自分がそこに居ていい存在理由』ができます。
よって話を面白くしたり、実際に起きたこと以上に誇張したりして、仲間内での存在価値を高めようとします。
承認欲求・注目を集めたい気持ち
大人と違い、まだ自分の経験が少ないぶん、インパクトのある話題を提供することで「自分は特別である」と感じたいという欲求が表れやすいです。反対に、自分を隠したいという防衛的な面も含まれています。
客観的事実より「受けた印象」で語りがち

思春期は感情の揺れ幅が大きくなり、普段よりも物事を敏感に感じ取りやすい時期です。たとえば、友だちとのちょっとしたケンカでも、「すごく文句を言われた!」「かなり酷いことを言われた!」と強く思い込んでしまう。
そして、その感情のままで周囲に話してしまう場合があります。実際にはそこまで深刻な状況ではなかったのに「こんなにつらかった」「とっても傷ついた」などと――悪意はないのだけど――誇張して伝えてしまうことで、事実との食い違いが生じやすくなることは少なくありません。
社会的比較やSNSの影響
SNSなどの台頭により、バズる情報を発信したい! 目立ちたい! という気持ちがとくに強まるのも思春期特有です。
ネット上ではよりドラマチックな出来事や映像・演出のほうが注目を集めやすいため、ついつい“盛って”しまう傾向は高まりやすいです。
思春期の男女が事実を“盛る”背景には、
- アイデンティティの確立
- 仲間や世間からの承認欲求
- 自己肯定感の揺れ
など、成長過程ならではの心理要因が大きく関わっています。
大人から見ると「ウソ」「大げさ」「やりすぎ」に思えることも、思春期の彼らにとっては自己表現の一環であり、周囲の評価を得るための戦略のようなもの。ウソといえばウソになるのかもしれませんが、愛らしい自己演出です。
ただし、注意が必要な問題が隠れているケースもあります。