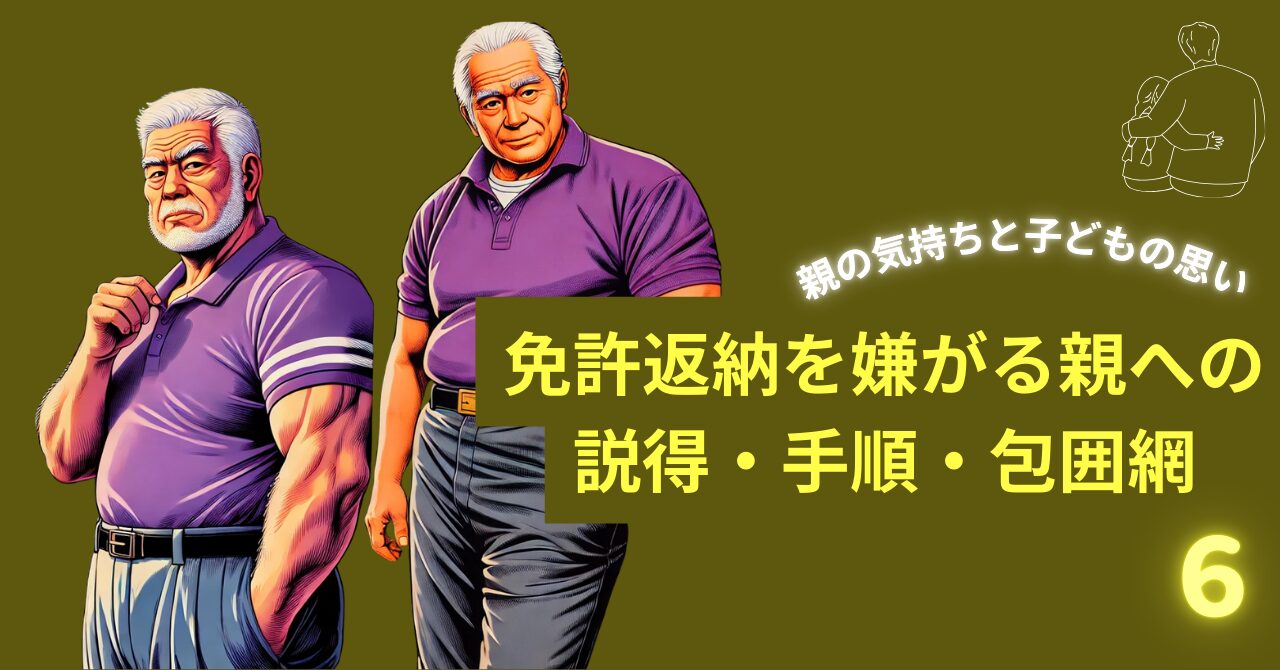こんにちは。「高齢ドライバーの免許返納、どう説得する?」シリーズ、しばらく時間が空いてしまいましたが、第6話をお届けします。
前回までの5回で、私たち家族が高齢ドライバーだった父に免許返納を促すために踏んだ具体的なステップや心構えについて、ひとつひとつまとめてきました。
(過去記事リンク:第1話 / 第2話 / 第3話 / 第4話 / 第5話)
第5話の最後で「次回は今だから思う気づきなどをまとめたいと思います」とお伝えしましたが、今回はその「気づき」に加えて、最新の状況を踏まえた情報もお届けしたいと思います。
最新データから見える高齢ドライバー事故の現実
まず、最新の状況について触れないわけにはいきません。警察庁が公表しているデータを見てみましょう。
警察庁交通局が発表した「令和5年中の交通事故の発生状況」によると、75歳以上の運転者が第一当事者となった死亡事故件数は384件で、これは全死亡事故の17.3%を占めています。
特筆すべきは、免許保有者10万人あたりで見ると、75歳以上の死亡事故件数は5.7件と、75歳未満(2.4件)の約2.4倍にものぼるという事実です。(出典:警察庁交通局 令和5年中の交通事故の発生状況について)さらに事故原因を見ると、75歳以上ではハンドル操作やブレーキ・アクセルの踏み間違いといった「操作不適」が30%と最も多く、加齢による運転能力の変化が事故に結びつく可能性を示唆しています。〔出典〕警察庁交通局「令和5年中の交通事故の発生状況について」警察庁「運転免許統計 令和5年版」
これらの数字は、決して他人事ではありません。
もちろん、多くの高齢ドライバーは安全運転を心がけていらっしゃいます。しかし、加齢による身体能力や認知機能の変化は、誰にでも起こりうること。それが運転に影響を及ぼす可能性は、統計データが示唆している通りです。
これらのデータから見える問題点は、単に「高齢者の運転が危ない」ということだけではありません。
- 事故原因の偏り 操作ミスが多いということは、とっさの判断や複雑な操作が難しくなっている可能性を示唆しています。
- 被害の大きさ ひとたび事故が起これば、ご本人だけでなく、他者の生命や財産を脅かす大きな被害につながりかねません。
- 社会的な不安 高齢ドライバーによる事故の報道は、社会全体の不安感を高め、時に過剰な反応を引き起こすこともあります。
こうした状況を踏まえると、やはり適切なタイミングでの免許返納は、ご本人、ご家族、そして社会全体にとって重要な選択肢であると言えるでしょう。
高齢者ドライバーの父の免許返納に向き合って、今だから思うこと
さて、ここからはこのシリーズを通して、そして皆様からの反響を通して感じた「気づき」についてお話ししたいと思います。
1. 「説得」は「対話」から始まる
続きを読む
シリーズでは「説得」という言葉を使いましたが、実際に重要なのは一方的な説得ではなく、双方向の「対話」なのだと改めて感じます。
本人の気持ち、運転を続ける理由、返納への不安… それらを丁寧に聞き、理解しようと努める姿勢がとても重要でした。へそを曲げられるとあとあと苦労するのはこちらです…。
「頭ごなしに否定しない」「感情的にならない」という基本がいかに大切かを痛感しました。
2. プライドと生活への影響への配慮
続きを読む
長年運転してきた方にとって、運転は単なる移動手段ではなく、自信や自立、社会との繋がりの象徴でもあります。
返納を促すことは、その方のプライドを傷つけたり、生活が一変してしまうことへの不安を煽ったりする可能性があります。
そのデリケートな感情への配慮を忘れてはいけなかったなと。
「運転できなくなったら、どうやって生活するの?」という具体的な不安に対し、代替案(公共交通機関、タクシー券、家族の送迎、宅配サービスなど)を一緒に考えるプロセスが不可欠です。
3. 「今すぐ」ではなく「段階的に」
続きを読む
すぐに返納を決断できる方ばかりではありません。
「夜間や雨の日の運転はやめる」「慣れた道だけにする」「家族が同乗する時だけ運転する」など、段階的なアプローチが有効な場合もあります。
もちろん安全が最優先ですが、ご本人が納得感を持って次のステップに進めるよう、焦らず、根気強く関わっていく必要があります。
4. 家族自身の葛藤と覚悟
続きを読む
返納を勧めるご家族自身も、大きな葛藤を抱えています。
「親不孝だと思われないか」「関係が悪化しないか」「返納後のサポートは本当にできるのか」… 様々な不安があるでしょう。
これは家族にとっても大きな決断であり、相当な覚悟とエネルギーが必要です。
一人で抱え込まず、兄弟姉妹や他の親族、場合によっては地域包括支援センターなどの専門機関に相談することも大切です。
5. 返納は「終わり」ではなく「始まり」
続きを読む
免許返納は、決して「終わり」ではありません。
運転から解放されることで、事故の不安がなくなり、新しい移動手段や趣味を見つけるきっかけになるかもしれません。
「安全で安心な新しい生活の始まり」と捉え、前向きな側面を伝えることも、ご本人の気持ちを後押しする一助となるでしょう。
まとめ:愛情と敬意のみえる話し合いを

高齢ドライバーの免許返納は、非常に複雑で感情的な側面も大きい問題です。最新のデータは私たちに現実を突きつけますが、それだけで解決する問題ではありません。
このシリーズを通して私たち姉弟が学んだのは、ステップや説得のテクニック以上に、本人への愛情と敬意を示すこと、そして根気強い対話がいかに重要かということです。
また、免許返納の説得や対話に至るまでに、こまめに連絡を取り、できるお世話は定期的にしておくことがいかに重要であったか。やはりここに「信頼」や「信用」「娘や息子たちは普段から自分の身を案じてくれていた」「厄介ごとを事前に排除しておこうという考えを、押しつけられているわけではなかった」と父が気づいてくれたことは大きかったと思います。
もし今、ご高齢のお父様やお母様をはじめとするご家族の運転に不安を感じていらっしゃるなら、どうか焦らず、この記事で触れた「気づき」等も参考にしていただきながら、ご本人様との対話を始めてみてください。
それは、ご本人様とご家族の皆様、社会全体の安全な未来を守るための大切な一歩となるはずです。
免許返納を最後は自分の意思で決めて行った父は「もうこれで絶対に事故を起こさなくて済む」と心からホッとしたと言っていたそうです。
これを人づてに聞いた時と、父から「ありがとう」と言われた時に、やっと報われた思いがしました。最後までお読みいただき有難うございました。私にできることがございましたら、お問い合わせくださいませ!