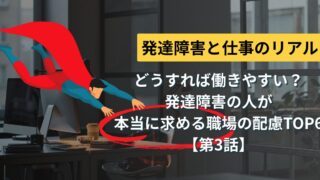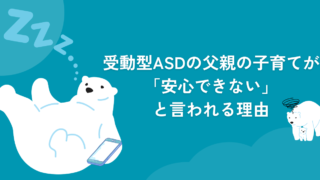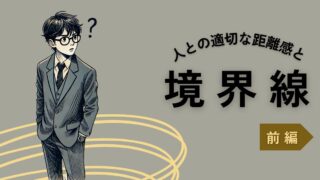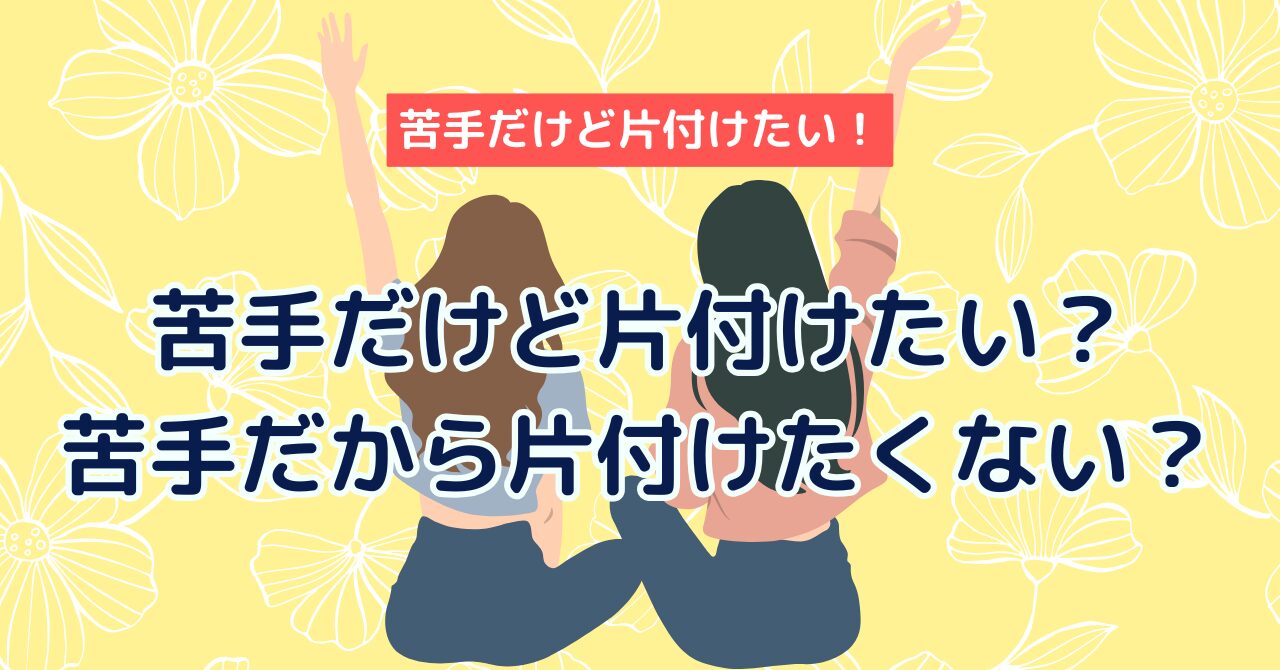「部屋を片付けたいのに、どこから手をつけていいかわからない…」
「何度片付けても、すぐに散らかってしまう…」
「もしかして、これって私の性格のせい? それともADHDの特性が関係してるの…?」
そんなふうに、片付けに関して一人で悩みを抱えていませんか?
まずは、片付けが苦手だと感じている女性たちがどんな理由を抱えているのか、アンケート調査の結果を見てみましょう。きっと「わかる!」と共感するポイントがあるはずです。
「片付けが苦手な理由」- 20代から50代の女性調べ
1位:とにかく物が多い タップで詳細
「物の量が多すぎて収拾がつかない」「何から手をつけていいかわからない」と感じる人が多数。
👉 153人
2位:物を捨てられない タップで詳細
「もったいない」「思い出がある」など感情面で捨てる決断ができないという声。
👉 135人
3位:面倒で後回しにしてしまう タップで詳細
忙しさや気力不足から「今度でいいや」とつい放置しがち。
👉 90人
4位:片付ける時間がない タップで詳細
仕事・家事・育児などで物理的に時間が確保できないという現実的な問題。
👉 77人
5位:収納スペースが足りない タップで詳細
「片付けようにも入れる場所がない」と悩む人も。賃貸住宅や古い間取りで特に多い傾向。
👉 38人
6位:捨てていいか判断できない タップで詳細
「いつか使うかも」「まだ使えるかも」と迷ってしまい、結局手が止まるパターン。
👉 31人
7位:片付いていなくても支障がない タップで詳細
「散らかっていても生活できるから…」と片付けの必要性を感じていない人も少数派で存在。
👉 18人
出典:woman.mynavi.jp(2023年公開調査より)
なぜ? 片付けが続かない「あるある」な理由と陥りやすいワナ
ランキングを見て、「うんうん、わかる!」と頷いた方も多いのではないでしょうか。では、なぜ私たちは片付けでつまずいてしまうのでしょう?
そこには、いくつかの「あるある」な理由や、知らず知らずのうちに陥ってしまっている「片付けのワナ」があるのかもしれません。
完璧主義のワナ ➤「やるなら徹底的に!」がプレッシャーに タップで詳細
「どうせやるなら完璧に片付けたい!」その意気込みは素晴らしいけれど、ハードルを上げすぎて最初の一歩が踏み出せなかったり、途中で息切れしてしまったり…。少しでも乱れると「もうダメだ…」と諦めてしまうことも。
一気にやろうとするワナ ➤エネルギー切れで挫折しやすい タップで詳細
「よし、今日こそ全部片付けるぞ!」と意気込んでも、物の多さや作業の終わりが見えないことに圧倒されて、途中で疲れてしまう…。そして中途半端な状態で自己嫌悪…なんて経験ありませんか?
とりあえず収納するワナ ➤見えない場所に詰め込むだけでは解決しない タップで詳細
とりあえず空いている箱や引き出しに物を詰め込んで、見た目だけスッキリさせる。でも、それは一時的な解決にしかならず、根本的な物の量は減っていないため、すぐにリバウンド…。どこに何があるかわからなくなることも。
自分に合わない方法を試すワナ ➤流行の片付け術が万能とは限らない タップで詳細
テレビや雑誌で紹介されている片付け術を試してみるけれど、なぜか自分にはしっくりこない、長続きしない…。人それぞれ性格やライフスタイルが違うように、片付け方も「自分に合った方法」を見つけることが大切です。
「見えない化」のワナ ➤ADHD特性との関連も タップで詳細
ADHDの特性として、視界に入らないものは「存在しないもの」として認識されやすいことがあります。そのため、引き出しや箱の中にしまった物は忘れ去られ、同じような物をまた買ってしまう…というループに陥りがち。結果、物は増える一方に。
これらの「ワナ」に心当たりはありませんか? でも、大丈夫。こうした傾向を知ることも、解決への第一歩です。
リモートお片付けご利用|相談者さん(ADHD特性あり)の場合
「片付けたいのに、どこから手をつけていいかわからない」「いろいろ試してみたけれど、長続きしない」――そんな悩みを抱える方は少なくありません。特にADHDの特性を持つ方にとっては、片付けはさらに難易度が高いと感じられることもあるでしょう。
ここで、ADHDの特性を持つある相談者さんとのリモートお片付けサポートの事例をご紹介します。彼女の抱えていた悩みや、実際に取り組んだステップが、あなたの片付けのヒントになるかもしれません。
1. 相談者さんの悩み:「部屋を見せるのが怖い…写真もビデオ通話もNG」
ご相談当初、彼女はこうおっしゃいました。
「片付けのスタート地点がわからなくて困っています。色々な片付け術を試したけれど、どれも続きませんでした。部屋の状態がひどくて、写真を撮るのも、ビデオ通話で部屋を見せるのもどうしても抵抗があります…」
通常、リモートお片付けの依頼者の方には「現在のお部屋」を見せてください、とお願いすることが多いです。しかし、こちらの女性と同じように『NG』を出される方はわりと多いです。
お部屋を見せることへの抵抗感、すごくよく分かります。片付けが進まない自分を責めてしまったり、恥ずかしいと感じてしまいますよね。このため、まずはじっくりとお話を伺い、間取りや普段の生活動線などを丁寧にヒアリングすることから始めました。
💡写真やビデオがなくても、言葉で状況を共有し、頭の中で部屋のイメージを組み立てます。
2. 大切なのは「余計なアクションを減らす」こと
片付けの基本は、「普段の行動動線をスムーズにする」こと。床が物で埋まっていると、歩きにくいだけでなく、それだけで片付けのやる気も削がれてしまいますよね。
そこで、最初の目標はシンプルに「床を見えるようにする」と定めました。
3. 実践ステップ:「まずは床!」から始める小さな一歩
床にある物を、ざっくりグループ分け タップで詳細
「完璧じゃなくてOK!」が合言葉。床に散らばっている物を、例えば「趣味のもの」「服」「書類」「カバン」「読みかけの本」など、本当に大まかなカテゴリーで分けていきます。
大きな紙袋や空き箱を用意し、カテゴリごとにポイポイ入れていくだけでも、床のスペースはみるみる確保できます。 大切なのは、細かく分類しすぎず、まずは「床から物を持ち上げる」ことです。
「使う場所」の近くに「使う物」を置く タップで詳細
グループ分けしたものを、それぞれ「よく使う場所」の近くに仮置きしてみましょう。例えば、毎日使うカバンは玄関の近く、読みかけの本はソファの横、など。
ポイントは、使った後に「戻す」というアクションが増えないように、自然な動線上に収納場所や置き場所を作ること。「あれ、どこにしまったっけ?」を探す手間や、「戻すのが面倒…」という気持ちを減らす工夫です。
4. ADHDの特性に寄り添う「片付け中断のサイン」に気づく
ADHDの特性がある方(もちろん、そうでない方も!)が片付けに取り組むとき、特に気をつけたいのが脳の疲労度です。「苦手なことに挑戦している」――それだけで、本当にすごいんですよ✨
片付けはゴールではなく、心地よい日常のための一つの作業。今日1日で全てをやり切る必要なんてありません。私がリモートお片付けの依頼をうけて大切にしていることは、相談者さんに以下のような様子がうかがえたら――通話ごしに聞こえる声や足音で確認・ビデオ通話ごしに目視――ストップの声掛けをしています。
- 「疲れてきたな…」と感じるサインの例
- 返事が「うん」「はい」だけになる
- 急に黙り込んでしまう、または逆に多弁になる
- 集中力が明らかに途切れている感じがする
- イライラしたり、そわそわし始めたりする
- 勇気をもって「中断する」メリット
- 疲労がピークに達する前に切り上げることで、片付けに対するネガティブな感情を防ぎ、次回へのハードルを下げます。
- 「今日はここまでできた!」という小さな達成感を積み重ねることで、自己肯定感が育ち、片付けを「続けられる仕組み」を作っていけます。
5. 「今日はここまで!」が、次へのモチベーションに繋がる
「途中で止めるなんて、中途半端じゃない…?」と思うかもしれません。
でも、得意ではない作業ほど「やめ時を決める」ことが、実はとても大切なんです。無理に片付けを続けて、その後の家事や仕事、大切な休息の時間に必要なエネルギーまで使い果たしてしまっては本末転倒ですよね。
何度も言いますが、苦手だと感じている片付けに一歩踏み出してチャレンジした――それだけで、ほんとにすごいことなんですよ✨ 私は虫が大の苦手なんですが、チャレンジがてらに触ろうとさえ思いませんもの。
「心地よい暮らし」の一歩を踏み出そう
- 完璧を目指さなくて大丈夫。まずは「床が見える」状態を目指してみましょう。
- 「使う場所」に「使う物」を置く意識で、余計なアクションを減らす工夫を。
- 疲れたら、勇気をもって「今日はここまで!」。小さな成功体験を重ねることが何より大切です。
- 自分に合ったペースと方法を見つけることが、心地よい空間への近道です。
少しずつでもステップを踏めば、必ず今よりも心地よい空間に近づけます。
もし1人で抱えきれないと感じたら、リモート片付けのように専門家のサポートを頼ってみるのもひとつの方法です。写真やビデオがなくても、あなたの気持ちに寄り添いながら、一緒に解決策を見つけていくことができますよ。
あなたらしい「心地よい暮らし」への小さな一歩を、今日から踏み出してみませんか?
✍オンラインカウンセリング「あたらしい今日」主宰・カウンセラー真由