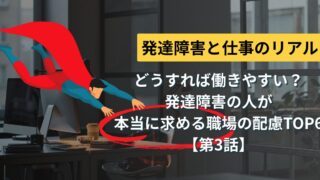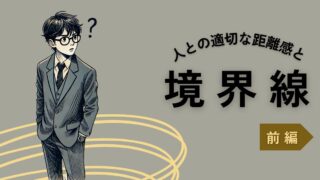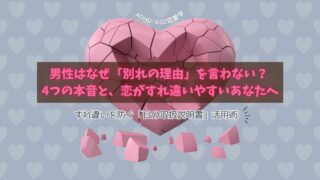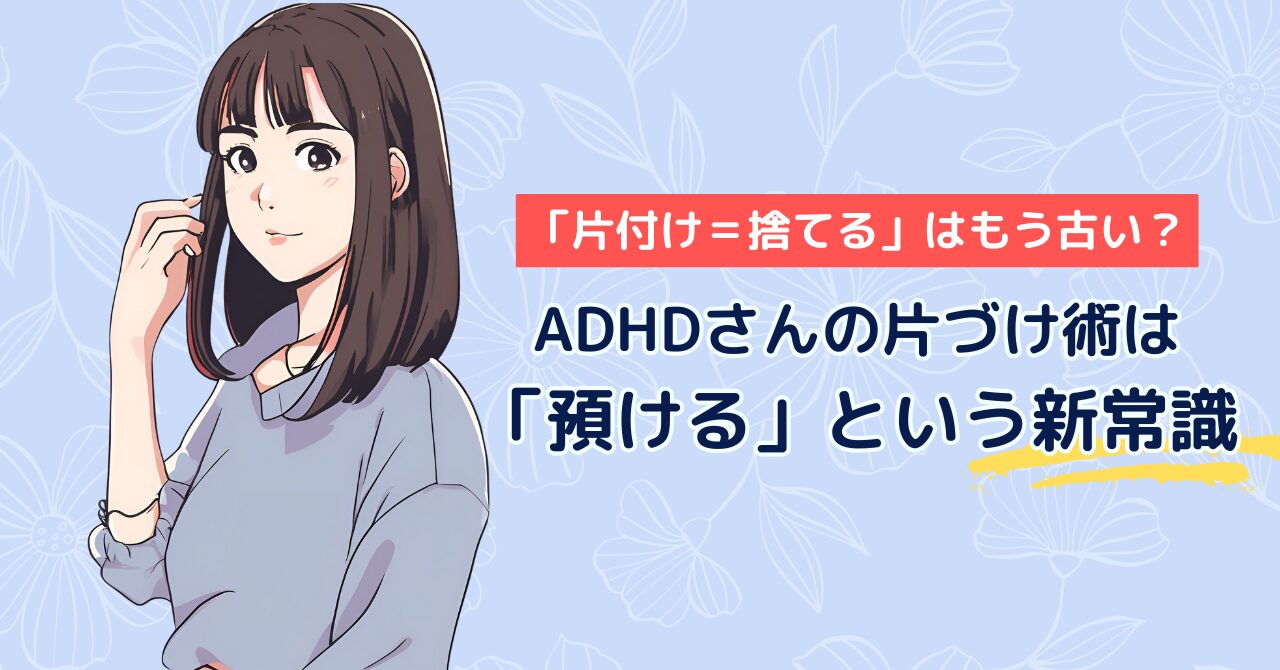「部屋を片付けたいのに、どうしてもモノが捨てられない…」
そんな風に悩んでいらっしゃいますか? 「今度こそ!」と片付け本を読んだり、人気の方法を試したりしても、結局リバウンドしてしまう…。
ADHDやASDなどの発達障害の特性を持つ方にとって、「捨てる」という行為は大きな心理的ハードルになることがあります。今回は、「捨てる」以外の新しい選択肢、「預ける」片付け術で、無理なくスッキリした部屋を目指す方法をご紹介します。

片付け本を何冊も読んで、書いてある通りにやってみるんです。でもいつも数日で元通り…。どうして私だけ上手くいかないんだろうって落ち込みます…
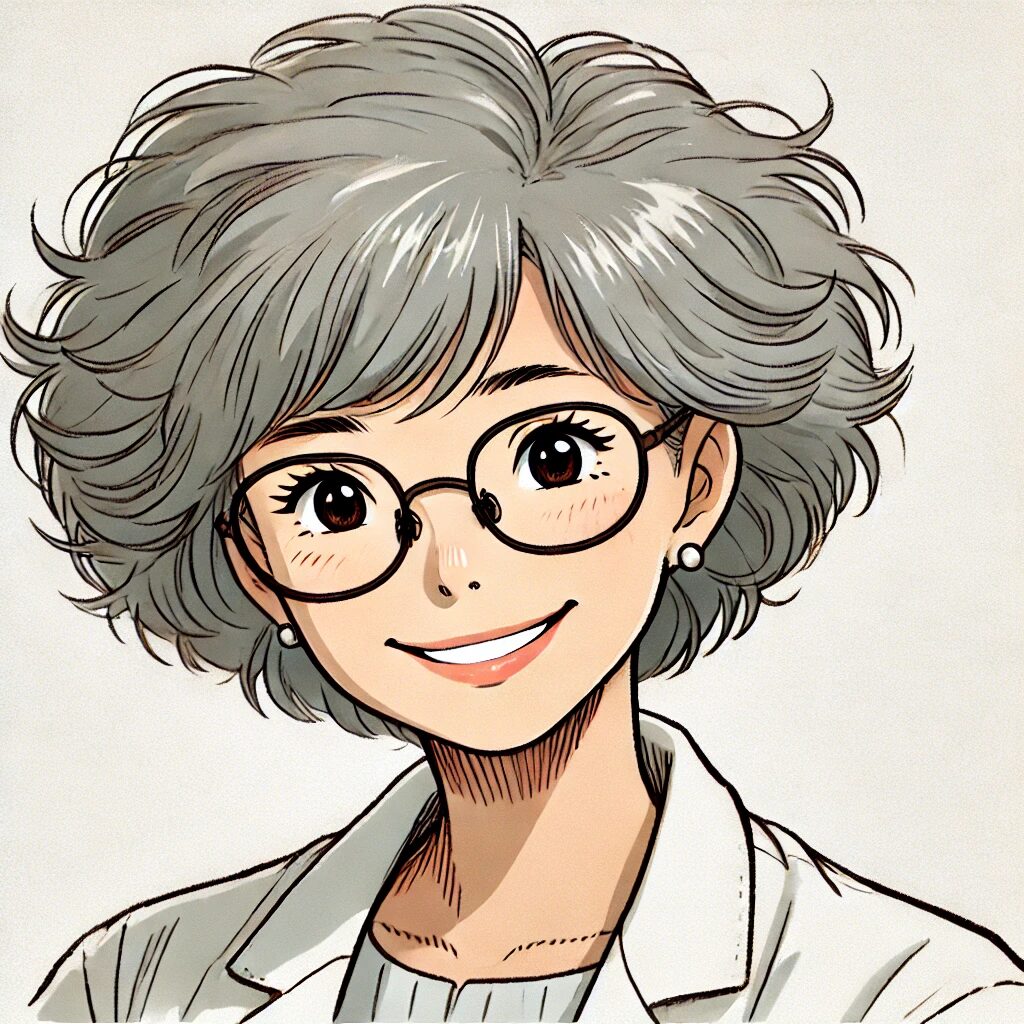
何度も挑戦していること、それ自体が素晴らしいですよ! 上手くいかないのは、やり方が合っていないだけかもしれません。あなたの特性に合った方法なら、きっと変わりますよ

そうだと嬉しいです…。でも、片付いた状態が本当に続かないんです
1.なぜ「捨てる」片付けがうまくいかないの?罪悪感とストレスのループ
片付けというと「使わないモノは捨てる」というルールがよく挙げられますよね。例えば「1年使っていない服は処分する」など。でも、この「捨てる」という判断が実はとても難しいのです。
- 「まだ使えるかもしれないし…」
- 「思い出があって、捨てるのは忍びない…」
- 「高かったから、もったいない…」
こんな気持ちが湧いてくると、捨てるたびに心がチクチク痛んだり、罪悪感をおぼえてしまいます。
この罪悪感や「捨てなければならない」というプレッシャーが、片付けそのものを苦痛なものに変えてしまい、結局「もうやりたくない…」と手が止まってしまう大きな原因なのです。
2.「捨てる」から「預ける」へ!心が軽くなる新発想とそのメリット
そこで提案したいのが、「捨てる」のではなく「一時的に預ける」という方法です。
「今は使わないけれど、家には置いておけない…」そんなモノたちを、外部の収納サービス(例えば、段ボール1箱から預けられる宅配型トランクルームなど ※わが家はサマリーポケットを長年使っています――に任せてみましょう。
この「預ける」という選択には、こんなメリットがあります。
「捨てるわけじゃないから大丈夫」と思えるので、心理的な負担が格段に減ります。思い出の品や趣味のコレクションも、手放すことなく保管できます。
家からモノが減るので、確実にスペースが生まれます。床が見えるようになると、気分もスッキリします。これ正直かなり爽快です✨
多くの宅配トランクサービスでは、預けたモノを写真でリスト化してくれたり、アイテムごとに管理できたりします。「あれはどこにやったっけ?」がなくなり、安心です。
「やっぱりあれが必要になった!」という時も、手続きすれば自宅に送ってもらえます。「捨てて後悔するかも」という不安からも解放されます。最短で翌日には届きます✨
「捨てなくていいんだ!」と思えるだけで、気持ちに余裕が生まれませんか? モノを物理的に移動させることでお部屋も心もスッキリし、片付けへの苦手意識が和らぎます。
3.実践!「預ける」片付けで床はどう変わる?具体的なステップと変化
ここでは、実際に「預ける」片付けを試した相談者さんの例を見てみましょう。まず、何から手をつけるか、どう進めるかがポイントです。
ステップ1:まず「床の上にあるモノ」に注目!ざっくり仕分けよう
部屋を見渡して、床に直置きされているモノをリストアップします。細かく分類する必要はありません。大きなカテゴリーでOKです。
- A. 創作系の趣味の作品や道具(例:絵、手芸品、プラモデルなど)
- B. 服(例:脱ぎっぱなしの服、シーズンオフの服の山)
- C. 洗濯物(例:取り込んだけど畳んでいないモノ)
- D. 文房具や細々したもの(例:ペン、ノート、充電器など)
- E. 書類や本(例:仕事の資料、読もうと思っている本、雑誌)
- F. チラシや郵便物
ステップ2:「今は使わないけど捨てられないモノ」を箱に詰めて預けよう
この相談者さんの場合、特に「A. 創作系の趣味の作品」が50個以上あり、床の大部分を占めていました。
これらは大切な作品なので「捨てる」ことは考えられません。そこで、これらをまとめて段ボールに詰め、宅配型トランクルーム(例:サマリーポケット)に預けることにしました。
ステップ3:どう変わった?「床が見える」ってこんな感じ!
変化1 趣味の作品(A)がごっそり減った! タップで詳細
変化2 床が見えた!スペースが生まれた! タップで詳細
変化3 「捨てなくていい」安心感で、気持ちが楽になった! タップで詳細
もちろん他のモノ(B~F)はまだ床に残っています。でも、一番場所を取っていたモノが移動したことで「床が見える!」という状態になり、次の片付けへの大きな一歩自信につながりました。
4.発達特性(ADHD・ASDなど)を持つ方が無理なく片付けを進める4つのコツ
発達障害の特性を持つ方は、脳の情報処理の仕方や集中力の保ち方などに特徴があるため、多く推奨されている片付け術が合わないことがあります。
ここでは、特性に配慮したより具体的で実践しやすい片付けのコツを4つご紹介します。これらは「預ける」片付けと組み合わせると、さらに効果的です。
1.「捨てる」プレッシャーをなくす工夫をする
- まず「預ける」「一時保管する」を前提に。「捨てるかどうか」の判断は後回しでOK。
- 「迷うモノ」専用の箱を作り、とりあえずそこに入れておく。その箱がいっぱいになったら預けることを検討。
2. 一度に考えること・やることを極力少なくする
- 「今日はこの棚だけ」「この引き出し1つだけ」と、範囲を限定する。
- モノを分ける時は、「よく使うモノ/あまり使わないモノ/預けるモノ」のように、2~3個の大きなカテゴリーから始める。
- タイマーを15分セットして、その時間だけ集中する。終わったら休憩。
3.「こうあるべき」という片付けの常識にとらわれない
- 「1年使わなかったら捨てる」が苦痛なら、無理に従わない。「預ける」でOK。
- 「全てのモノに定位置を」と頑張りすぎない。よく使うモノは、カゴに入れるだけの「ざっくり収納」でOK。
- 見た目の美しさより、自分が使いやすいか、続けやすいかを優先する。
4. 出し入れのアクション(手間)を最小限にする
- よく使うモノは、フタなしの箱に入れる、吊るすなど、1~2アクションで出し入れできるようにする。
- 引き出しの中も、仕切りを使いすぎず、ポイポイ入れられるスペースを作る。
- ラベリングをするなら、文字だけでなく、写真やイラストを使うと直感的に分かりやすい。※私個人的にはラベリングも写真やイラストの貼付もめんどくさいからやらなくていいと思います(笑)
5.「預ける」片付けで、今日から変わる!最初の一歩と続けるコツ
- 「捨てる」のが苦手なら、まず「預ける」を試してみよう!
罪悪感なく家の中のモノを減らせる、とても有効な方法です。 - 完璧を目指さない!まずは1カテゴリー、1箱からでOK!
一番場所を取っているモノや、一番ストレスに感じているモノの山を、段ボールに詰めて預けてみましょう。それだけで部屋の景色と気分が変わります。 - 疲れたら休む!自分のペースを大切に!
特に発達特性がある方は、集中しすぎるとどっと疲れてしまうことも。こまめに休憩を取りながら、無理なく進めるのが続けるコツです。
床にモノが山積みでどこから手をつけていいか分からない…そんな状態でも、まず「預ける」という選択肢を知るだけで、気持ちが少し楽になるはずです。
モノを「捨てる」か「捨てないか」で悩む前に、一度「家から出す(預ける)」ことを試してみてください。きっと、スッキリした空間と心の余裕を手に入れる第一歩になりますよ。
✍オンラインカウンセリング「あたらしい今日」主宰・カウンセラー真由