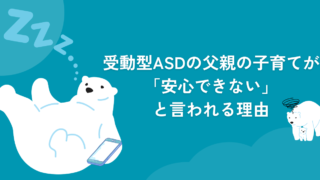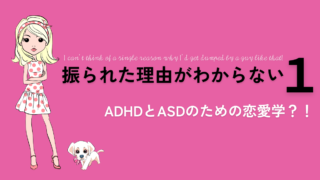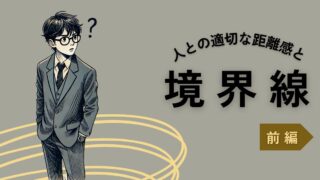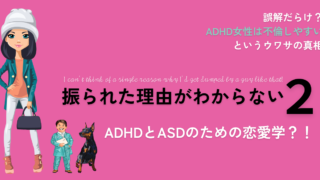苦手な片づけをプロに依頼したい|リモート片付けサポート事例4
「片付け」と「整理整頓」はセットで語られがちですが、実は別のアクションだとご存じですか? これらを混同してしまうと「とりあえず形は整ったのに、またすぐ散らかる…」という悪循環が起きやすくなります。そこで今回は、片付けと整理整頓の違いや、ADHDなど発達特性がある方に向けたサポートのポイントを紹介します。
1.「片付け」と「整理整頓」の違い
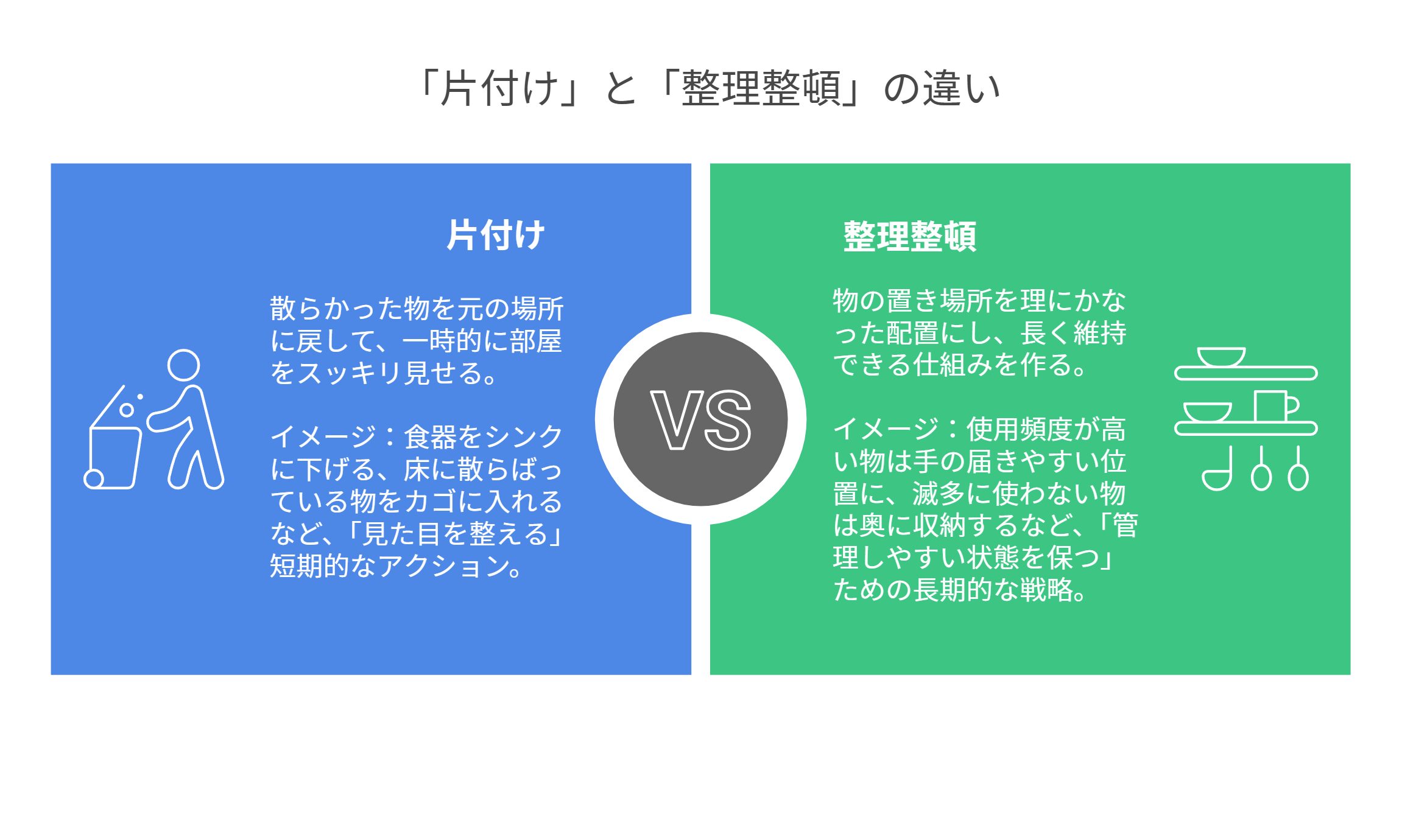
1-1.片付け
- 目的:散らかった物を元の場所に戻して、一時的に部屋をスッキリ見せる。
- イメージ:食器をシンクに下げる、床に散らばっている物をカゴに入れるなど、「見た目を整える」短期的なアクション。
1-2.整理整頓
- 目的:物の置き場所を理にかなった配置にし、長く維持できる仕組みを作る。
- イメージ:使用頻度が高い物は手の届きやすい位置に、滅多に使わない物は奥に収納するなど、「管理しやすい状態を保つ」ための長期的な戦略。
ポイント
- 片付け:その場をとりあえず整える。
- 整理整頓:使いやすさと維持のしやすさを考える。
2.ADHDなど発達特性がある人ほど「片付け」と「整理整頓」を分けて考える
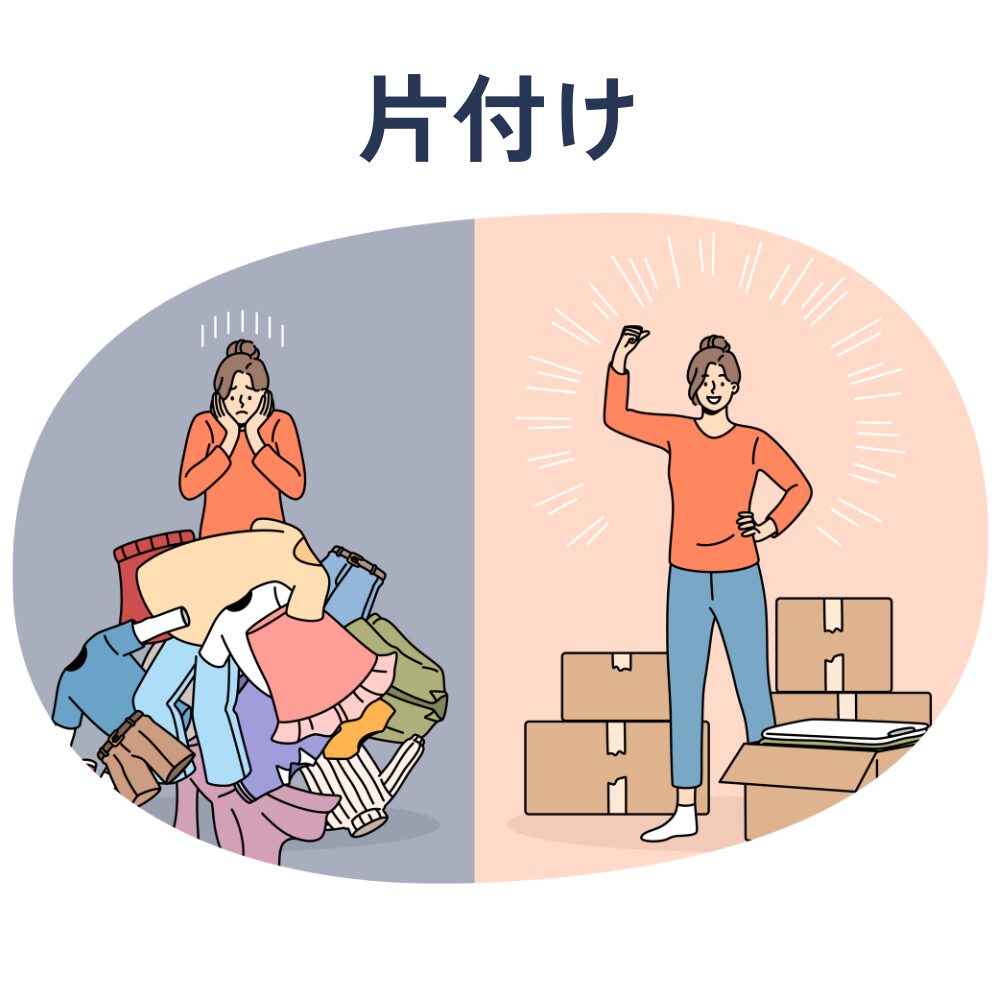

「片付け」には空間認知能力が、「整理整頓」には構造化能力(論理的思考・計画力・分類力・継続力)が求められます。ADHDやASDなどの特性がある方にとって、これらは別々に難しさを感じることが多いのです。
- 片付け(空間認知)
- 物の位置関係を把握しながら、元に戻す作業が苦手になりやすい。
- 整理整頓(構造化)
- 論理的に物の配置を考えたり、習慣化して維持するのが大変。
料理に例える「片付け」と「整理整頓」
- 片付け(短期的アクション)
- 料理におけるイメージ: 「とりあえず目の前の食材を切って、すぐ炒めたり焼いたりして一品を完成させる」
- 必要なスキル: 目の前の材料を瞬時に把握し、手早く調理する能力(=空間認知的な部分)
- 例: 「冷蔵庫にある野菜を適当に刻んで炒める」「とりあえず今日はパスタを茹でて済ませる」
- 整理整頓(長期的な仕組みづくり)
- 料理におけるイメージ: 「1週間分の献立を考え、必要な食材を買いそろえ、栄養バランスと調理の順番を計画的に組み立てる」
- 必要なスキル: 論理的思考、計画力、仕分け・管理能力(=構造化能力)
- 例: 「週末にまとめ買いをして献立を組み立てる」「平日は短時間で作れるよう下ごしらえをしておく」
3.整理整頓に必要な「4つのスキル」
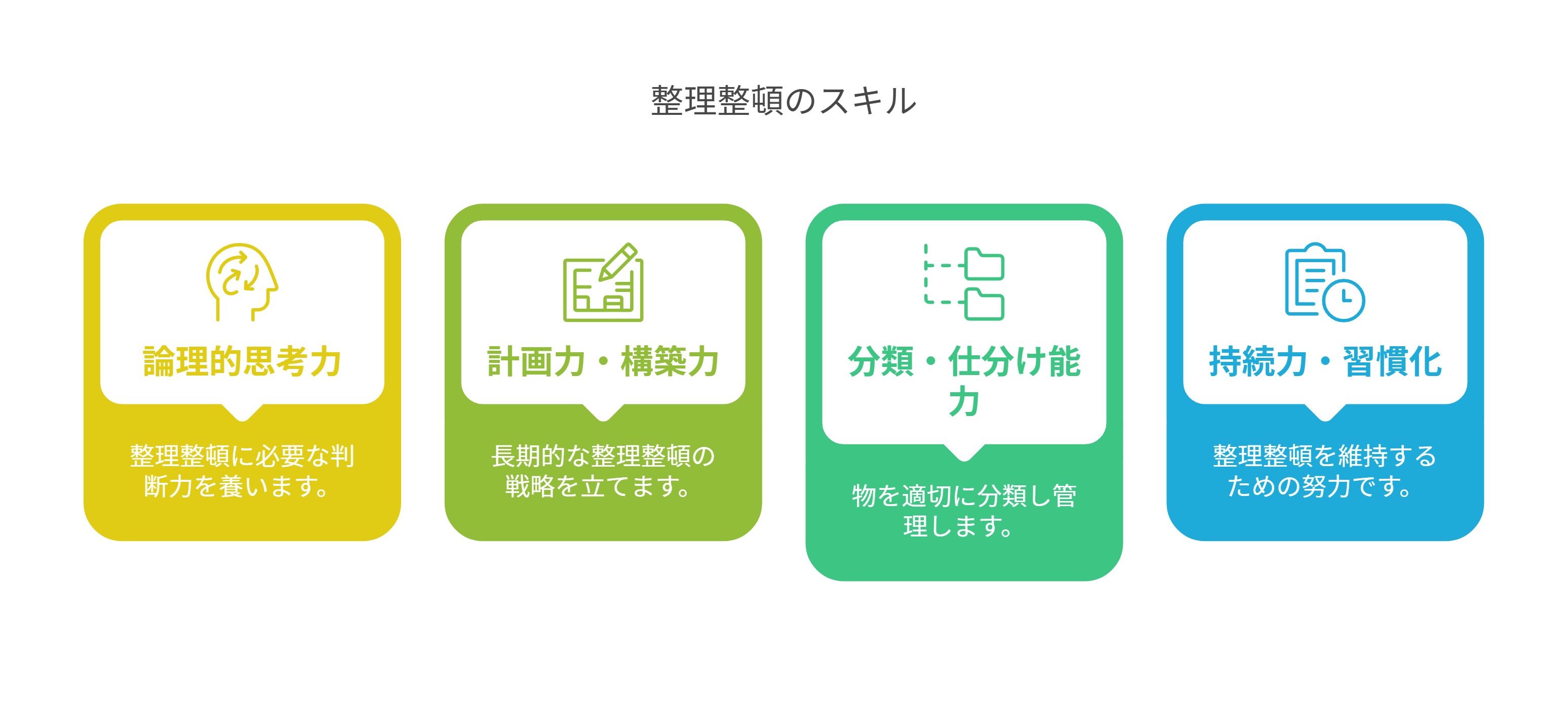
3-1.論理的な思考力
- 何を残して、何を処分するか
- どの順序で配置すれば使いやすいか
物を分類し、置き場所を決めるための判断力が必要です。
3-2.計画力・構築力
- 長期維持を見据えた配置づくり
- 配置の戦略をあらかじめ考える
使用頻度の高い物を手前に、低い物を奥へ…といった計画が欠かせません。
3-3.分類・仕分け能力
- どのカテゴリーに分けるか
- グループ化の基準をどうするか
分類が曖昧だと「物がどこにあるのか」わからなくなり、散らかりやすくなります。
3-4.持続力・習慣化
- 一度整えた状態を定期的に見直す
- 元の場所に戻す習慣を続ける
整理整頓は「作って終わり」ではなく、維持する努力が必要です。
4.リモート片付けレッスン:私がサポートすること
私は「リモート片付け」の先生兼カウンセラーとして、主に以下のような支援をしています。
- (1~3の段階) 論理的思考・計画力・分類方法のアドバイス
- (週1回のセッション) 習慣化をサポート
- 小さな成功体験を重ねてストレスを最小限に。
- 100点満点を狙うより、まずは70点をキープするイメージが大切です。
私のモットー
「得意を伸ばし、不得手には無理のないサポートを」
昔ながらの「努力・根性・精神論」だけでカバーするやり方は、得策とは言えません。苦手分野をただ頑張り続けると、本人も周囲も疲れ切ってしまい、“嫌い”の気持ちがどんどん大きくなります。まずは無理なく70点を取れる仕組みを一緒に作りましょう。
5.発達障害の特性による「片付け&整理整頓」のよくある困りごと
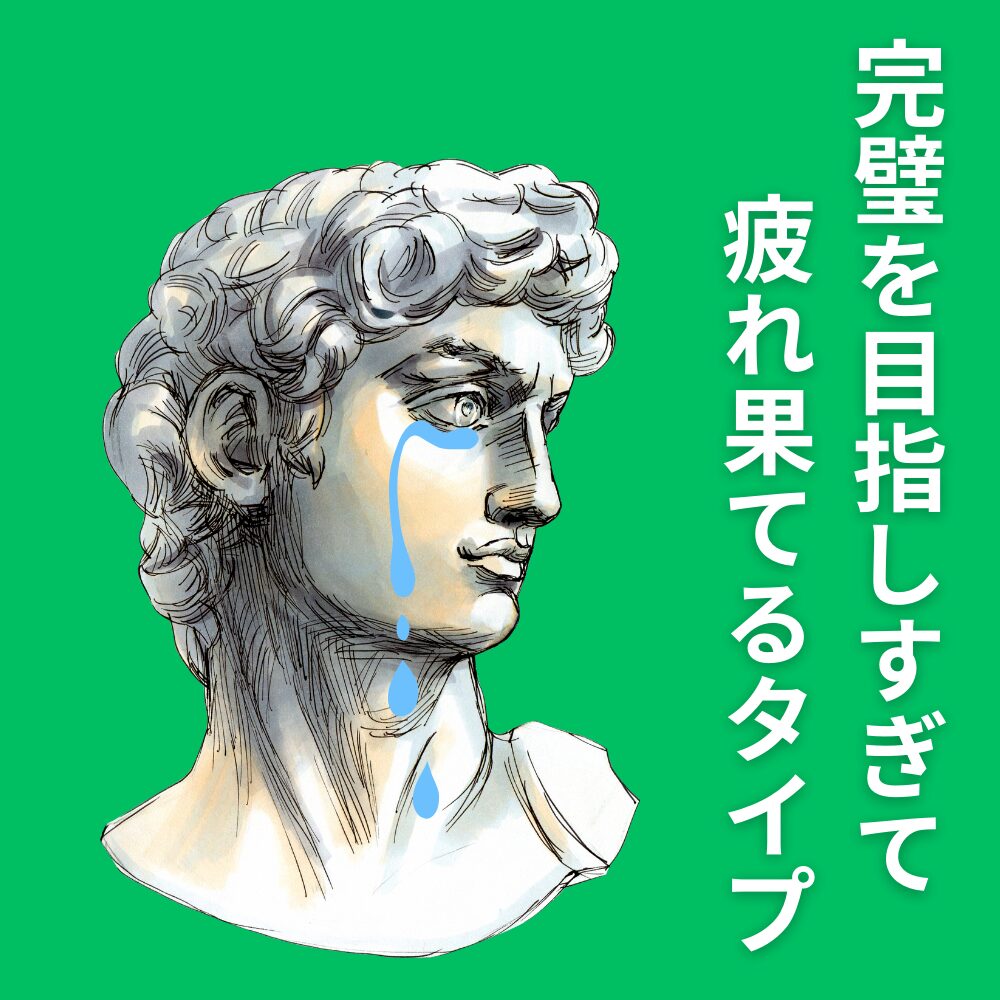

- ASD傾向が強い場合
- 物の分類やルールにこだわりすぎて、逆に整理整頓が複雑になることも。
- 完璧を目指しすぎて途中で疲れてしまうパターンが多い。
- ADHD傾向が強い場合
- 順序立てや計画的に物を定位置に戻す作業が苦手。
- 一度整理しても、気が散りやすく維持が難しい。
- 「やりかけ」状態のスペースがあちこちに点在しやすい。
6.ADHDさん向けの定番「4つの片づけ整理術」の隠れたハードル
よく挙げられる方法として、
- 視覚的サポート(ラベルや色分け)
- シンプルなルール設定
- エリアごとに片付け
- 置き場所を決める(物に住所を)
などがあります。
しかし、これらを実践するには最初から「ラベルを作る」「他の場所に気を取られず作業を続ける」といった多くのスキルが必要です。ADHDの特性により集中が途切れやすい方は、逆に「作業途中で気が散る」「分類作業を細かくしすぎて挫折」といった問題に陥りがちです。
7.まずは「70点」を維持することから
いきなり完璧を目指さず、少しずつステップを踏みながら、できるところから進めることが大切です。片付けに対して「苦手意識」を持っているならなおさら、無理やり頑張る方法より、専門家や周囲のサポートを上手に使ってみましょう。
- 片付け(短期的)と整理整頓(長期的)を分けて考える
- ADHDやASDなどの特性を認識し、自分のやり方に合った方法を選ぶ
- 最初から完璧にこだわらず、70点をキープする仕組みづくりを目指す
「片付けられない」と一人で悩むより、専門家のリモートレッスンなどを利用すれば、苦手分野をスムーズに補うことができます。ぜひ一度、気軽に相談してみてください。あなたの生活スタイルに合った「片付け&整理整頓」の方法がきっと見つかりますよ。
リモート片付けやカウンセリングにご興味のある方へ
「片付けなきゃ…でも、どうやって始めればいいかわからない」そんなときこそ、外部のサポートを頼ってみませんか? 一人では難しいプロセスでも、伴走者がいると意外なほどスムーズに進みます。まずはお気軽にご相談ください。