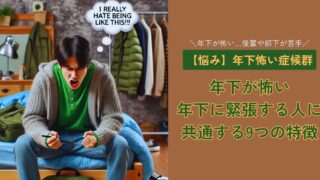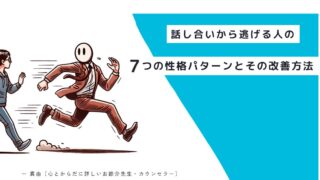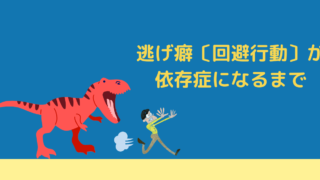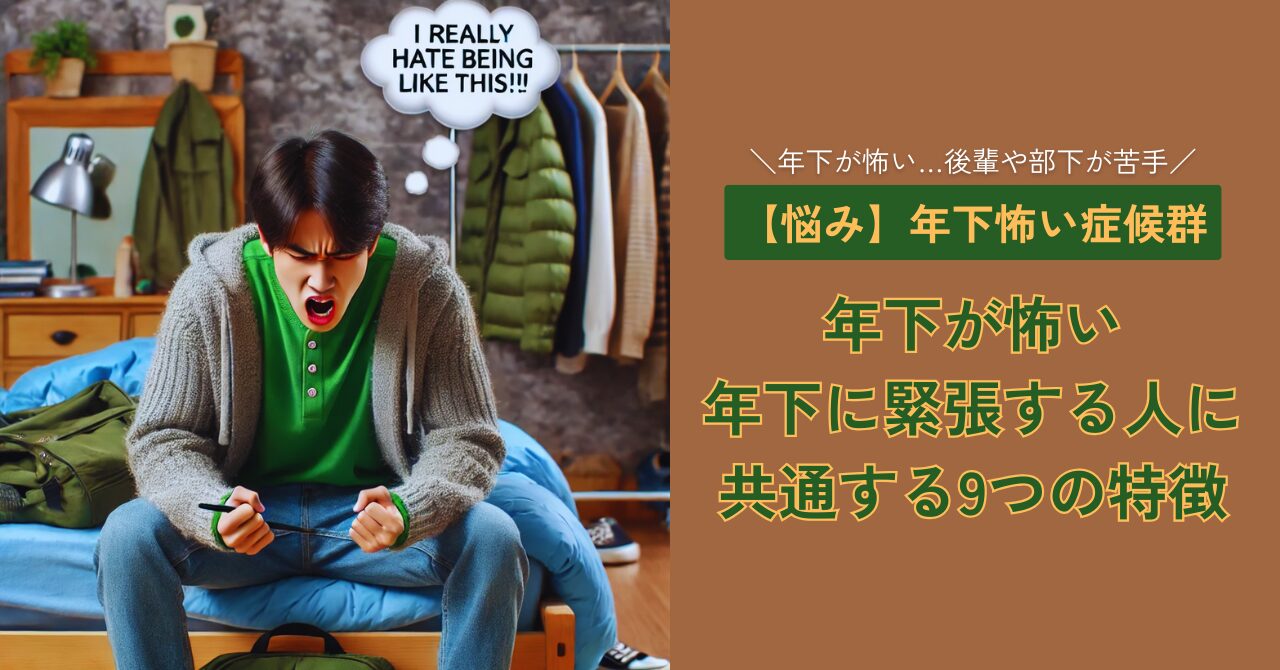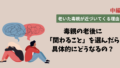「年下の後輩や部下が怖い…」「何を話せばいいかわからなくて緊張する…」「しっかりしなきゃってプレッシャーでしんどい…」
そんな風に悩んでいませんか?
実は10代後半から20代後半くらいの若い世代には、「年下が怖い」「苦手」と感じる人が意外と多いんです。だから、安心してください。その悩み…ここだけの話、多くの人が経験しています。
この記事では「なぜ年下が怖いと感じてしまうのか」そしてどうすればもっと楽に関われるようになるのかを、3つのステップで分かりやすく解説します。
大丈夫です。時間が経てば自然と慣れていくことも多いけど、「今すぐ何とかしたい!」というあなたのために、今日からできることをまとめました。
もしかして、あなたも?「年下怖い」あるあるチェック
まずは、自分に当てはまるかチェックしてみよう!
- □ 家族の中で一番年下だった(末っ子 or ひとりっこ)
- □ 年上のいとこや親戚が多く、可愛がられて育った
- □ 部活経験がない、またはすぐに辞めてしまった
- □ 人数の少ない部活や、異性の多い部活だった
- □ 中学・高校時代に、不登校や燃え尽きを感じた時期がある
- □ あまり地域のイベントなどに参加しなかった
- □ いつも年上の人に遊んでもらっていた
- □ すごくしっかり者の兄や姉がいる(自分と比べてしまう)
いくつか当てはまった人は、年下との接点や「先輩」としての経験が少なかったのかもしれません。これが「年下怖い」と感じる大きな原因のひとつです。
なんで年下が怖いの?主な原因はこの2つ!
「年下怖い」と感じるのには、大きく分けて2つの原因があります。
環境的な要因▶「年下」に慣れていないだけ! 続きを読む
チェックリストでもあったように、これまでの環境で年下と関わる機会が少なかったり、自分が年下でいることに慣れていると、いざ自分が「年上」の立場になった時にどう振る舞えばいいか分からず、戸惑いや怖さを感じてしまうんです。シンプルに「経験不足」なだけ、ということが多いです。
心理的な要因▶「完璧な先輩」にならなきゃ!というプレッシャー 続きを読む
「自分が年下だった頃、お世話になった先輩みたいに、しっかりしなきゃ」「頼りになって、面白くて、デキる先輩じゃないといけない…」
そんな風に、自分で「理想の先輩像」を作り上げて、そのプレッシャーに押しつぶされそうになっていませんか?
子どもの頃に見ていた「すごいお兄さん・お姉さん」のイメージが強すぎて、「自分もそうならなきゃ!」と思い込んでしまう。これが、緊張や苦手意識につながっている場合も多いんです。
でも、思い出してみてください。あなたの周りにいた年上の人たち、みんながみんなリーダータイプでしたか? 控えめだけど優しかった人、そっとサポートしてくれた人、いろんなタイプの人がいたはずです。
「年下怖い」を克服!3つのステップ
じゃあ、どうすれば年下への苦手意識を克服できるの?焦らなくて大丈夫。簡単なことから、3つのステップで試してみましょう!
【STEP 1】まずは「年下」に慣れることから始めよう!
- 意識を変える▶ 「怖い」「苦手」と思う気持ちはいったん横に置いて、「年下の子も、自分と同じように、ただ学校やバイト先、会社にいる一人の人間なんだ」と捉えてみましょう。
- 小さな接点を持つ▶ 無理に話しかけなくてもOK!まずは「おはよう」「おつかれさま」の挨拶から。目が合ったら、軽く会釈するだけでもいいんです。
- 観察してみる▶ 相手がどんなことに興味があるのか、どんな時に楽しそうか、少し観察してみるのも◎。共通の話題が見つかるかもしれません。
【STEP 2】完璧な先輩じゃなくてOK!「理想の先輩像」を手放す
「すごい先輩」を目指さない 続きを読む
リーダーシップを発揮したり、場を盛り上げたりするのが得意な人もいれば、聞き役が得意な人、黙々と作業するのが得意な人もいます。全員が同じである必要はありません。
自分の「得意」を活かす 続きを読む
あなたが得意なこと、自然にできることは何ですか? 話をじっくり聞くこと? 丁寧に作業を教えること? 面白い情報を見つけること? あなたの得意な方法で関わればいいんです。
昔の自分を思い出す 続きを読む
あなたが年下だった頃、どんな先輩に助けられましたか? どんな言葉が嬉しかったですか? それを今度はあなたが次の世代にバトンする、という視点を持つのもおすすめです。
【STEP 3】「ちょうどいい距離感」で関わってみる(具体的なアクション)
いきなり積極的に関わるのが難しくても大丈夫。こんな方法から試してみては?
- まずは「見守る」スタンスで(俯瞰)
少し離れたところから、年下の子たちが何をしているか、困っている様子はないか、そっと見守ってみましょう。 - 困っていそうなら「そっと」サポート(アシスト)
もし困っている様子が見えたら、「大丈夫?」「何か手伝おうか?」と声をかけてみる。難しければ、黙ってサッと手伝うだけでもOK。 - 直接が難しければ「間接的に」サポート(影のアシスト)
- 役立ちそうな情報や手順をメモに残しておく。
- 探していたものを、そっと分かりやすい場所に置いておく。
- 「〇〇さんが、これ探してたよ」と他の人に伝える。
こんな風に、自分にできる範囲で、さりげなくサポートすることから始めてみましょう。完璧じゃなくても、相手はきっとあなたの気遣いを嬉しく思ってくれますよ。
【補足】思春期の経験が影響している場合
中学・高校時代(特に14~15歳くらい)や、大学、社会人になりたての頃に、不登校やバーンアウト(燃え尽き症候群)、人間関係の変化などで「先輩」としての役割を経験する機会が少なかった場合、年下との関わりに戸惑いを感じやすくなることがあります。
これは、自転車の乗り方を練習なしでいきなり乗れないのと同じ。「先輩」になるにも、少しずつ経験を積んでいくことが大切なんです。焦らず、今の自分ができることから始めていきましょう。
心が軽くなるヒント:緊張や不安を和らげるカンタンな方法
年下と接する前に緊張してしまう…そんな時は、こんな方法で心を落ち着かせるのもおすすめです。
- 読書(活字):
マンガもいいけど、できれば小説や実用書など「活字」の本を読んでみましょう。研究によると、読書には筋肉の緊張を和らげ、心拍数を落ち着かせる効果があるそうです。短い時間でもOK!通学・通勤時間や、少し早めに行って始まる前に10分読むだけでも違いますよ。
焦らなくて大丈夫!あなたらしい関わり方を見つけよう
「年下が怖い」「苦手」と感じるのは、家族構成や学生時代の過ごし方などの環境や経験、そして「ちゃんとしなきゃ」という真面目さゆえの悩みです。
今回紹介した3つのステップは、
- 慣れること
- 完璧を目指さないこと
- 自分にできることから関わること
でしたね。
いきなり全部やろうとしなくて大丈夫。まずは「挨拶してみる」「遠くから見守ってみる」など、小さな一歩から試してみてください。焦らず、少しずつ経験を重ねていくうちに、きっとあなたらしい年下との関わり方が見つかるはずです。応援しています✨
✍オンラインカウンセリング「あたらしい今日」主宰・カウンセラー真由