傷ついた脳、傷つけられた脳
子どもの脳は、とても繊細で環境の影響を受けやすいものです。特に、日常的なストレスや不適切な関わりが続くと、脳の発達に悪影響を及ぼすことが分かっています。
親や養育者による「不適切な育児」「避けたほうがよい育児」、つまり マルトリートメント(マルトリ) を受けることで、子どもの脳が変形し、将来の心身の健康や行動に影響を与える可能性があるのです。
マルトリートメントとは?
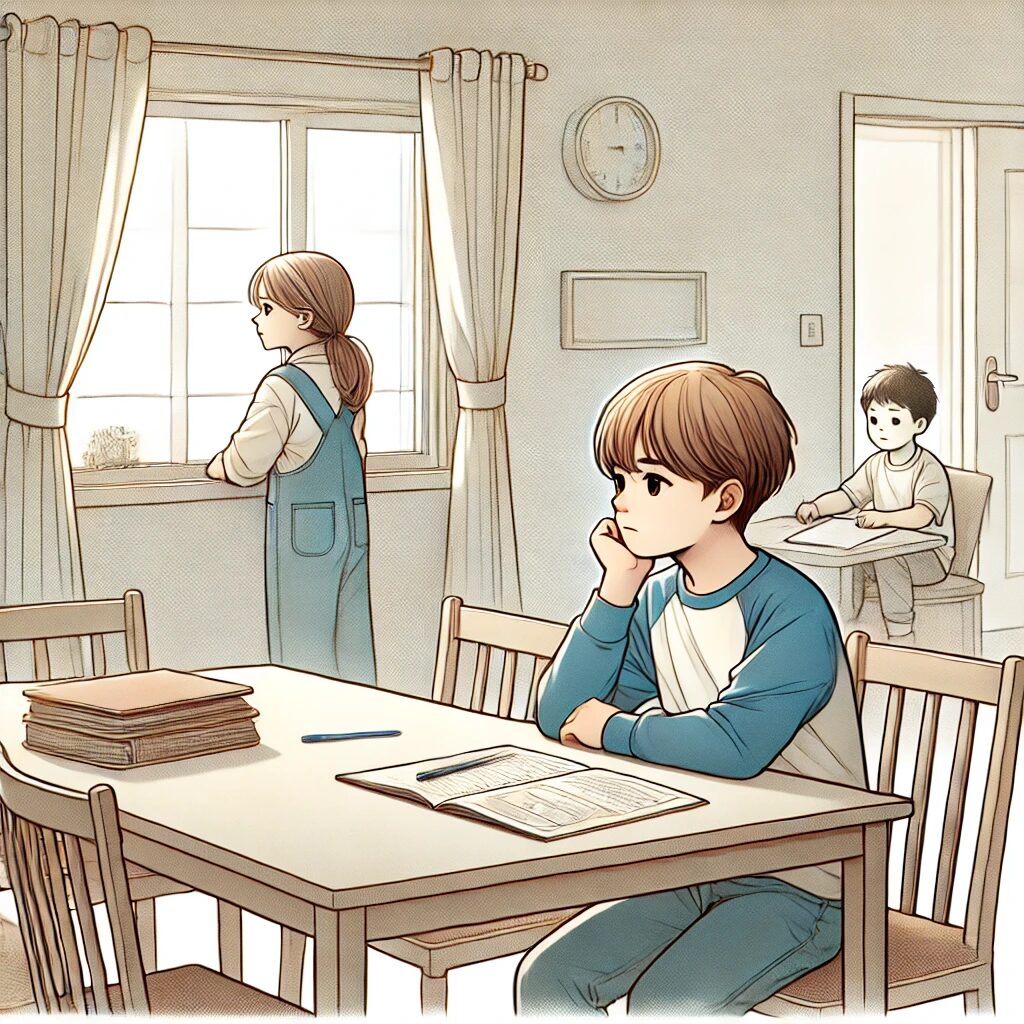
マルトリートメントは 「虐待」だけでなく、大人から子どもに対する避けるべき関わりすべてを指します。大人世代・親世代が見ると「え? これもマルトリートメント(不適切な育児)になるの?」と驚くようなものもなかにはあるかと思います。
昭和の時代は当たり前だった。こんなの普通のことだよ。うちの親なんてまさにこれだけど、俺はふつうに育ったよ! と、鼻で笑う親世代もいるでしょう。
あなたにとっては平気なことに、苦しみや憤り、さみしさを感じる人たちが「当たり前に居ること」を知ってください。あなたと相手は常にイコールではないんです。
こんなこともマルトリートメント?
子どもの心や体を傷つける行為は「虐待」だけではありません。
マルトリートメント(マルトリ)は、身体的虐待やネグレクトのように明確な虐待行為だけでなく、親や大人の「加害の意図」は関係なく、子ども本人にとって有害であることを指します。「しつけのつもり」「これくらい大丈夫」と思ってしまいがちな行動の中に、子どもを傷つける要素がたぶんに潜まれているんです。
① 言葉の暴力も子どもの心を傷つける
- 「なんでそんなこともわからないの?」
- 「○○ちゃんはできるのにね…」
- 「うちの子は本当に手がかかって困る」と第三者に言う
- 「もう〇歳なのにこんなこともできないの?」
- 「女の子なんだから~しなさい」
- 「男の子なんだから~しなくていい」
こういった言葉は、子どもから意欲を奪い、自己肯定感を奪い、萎縮させます。子どもは「自分はダメな子なんだ」「自分がぜんぶ悪いんだ」と思い込み、自信をなくしてしまいます。
ポイント
👉 その子を「誰か」と比較しないこと。
👉 できなかったことを嘆くのではなく、できたことを認め、称える言葉や感謝の言葉をかける。それが最優先です✨
② 夫婦喧嘩を見せること・「橋渡し」をさせること

子どもは、親の争いを見聞きすることで強いストレスを感じます。大声での口論、暴言、物を投げる行為などが日常的に行われると、子どもの脳は常に「危険を察知するモード」になり、落ち着いて過ごすことが難しくなります。
また、これはわりとよくあることかもしれませんが…夫婦間で話をしたくないからといって、子どもを会話の橋渡しにしてしまう。これは絶対にしてはいけないことです。
自分の言いたいことを飲み込んで、父親と母親、ひいてはきょうだいの気持ちまでもを「橋渡し」していたため『喉に拳大のストレス球』ができてしまい――感覚異常――10年間、まともに呼吸ができず非常に苦しんでいた患者さんがいました。
影響
- 情緒が不安定になる
- 他人との関係を築くことが苦手になる
- 言葉の暴力や暴力的な行動を学習してしまう
- 自分のせいで親が喧嘩をしているのではないかと罪悪感をおぼえる
- 肉体的DVを見るよりも、家族の暴言を(罵る・大声を出す)日常的に聞かされる方が子どもの脳には10倍近くの悪影響があります。
ポイント
👉 子どもの前での喧嘩は控え、話し合いは冷静に行う。
👉 もし言い争いになったら、後で「大きな声を出してごめんね」と伝える。
③ 体罰は子どもに「恐怖を与えて操縦」する行為

「しつけ」のつもりで叩いたり、厳しく怒ったりすることが、実は子どもの成長に悪影響を与えることが分かっています。
体罰の具体例
- 叩く、つねる、頭をこぶしでたたく
- 罰として長時間立たせる、正座をさせる
- 「お尻をたたく」ことも含まれる
- 罰として食事を与えない、お風呂に入れない
影響
- 怒られるのが怖くてウソをつくようになる
- 暴力を「しつけ」として学習し、友だちをいじめたり、自分よりも幼くて非力な存在(小動物を含む)に対して「親からされた暴力」を同じように繰り返すことがある
ポイント
👉 「叩く」のではなく、「話して伝えるしつけ」を心がける。
👉 子どもが間違えたときは、「どうすればよかったか」を一緒に考える。
④ スマホ育児の影響
現代では、スマートフォンやタブレットを子どもに与えて長時間使わせることが増えています。しかし、長時間の画面視聴は、子どもの発達に悪影響を及ぼす可能性があります。
影響
- 親子のコミュニケーション不足
- 言葉の発達の遅れ
- 感情のコントロールが難しくなる
ポイント
👉 スマホを育児の代わりにしない。
👉 子どもと一緒に遊ぶ時間を意識的に作る。
⑤ 放置(ネグレクト)も深刻な問題

ネグレクトとは、子どもに必要なケアを十分に行わないことを指します。
具体例
- 食事を与えない、栄養バランスを考えない
- 子どもが病気になっても病院に連れて行かない
- 学校や習い事を無断で休ませる
- 家に帰っても親がほとんど不在で放置される
- 歯磨きに関与せず、子どもに虫歯が増える
- 子どもが不潔な状態になっている
- 子どもだけで長時間の留守番を日常的にさせている
愛情や責任の欠如ではなく、養育者になんらかの事情があり養育能力に適切な支援が必要なケースもあります。例)養育者に知的な遅れや発達障害の傾向が見られたり、脳病があったり、病床に伏しているなど
影響
- 心身の発達が遅れる
- 人を信じることができなくなる
- 「自分は愛されていない」と思い込んでしまう
ポイント
👉 子どもに必要なケアをしっかり行う。
👉 育児がつらいと感じたら、行政や専門機関に相談する。
マルトリートメントによる脳の影響
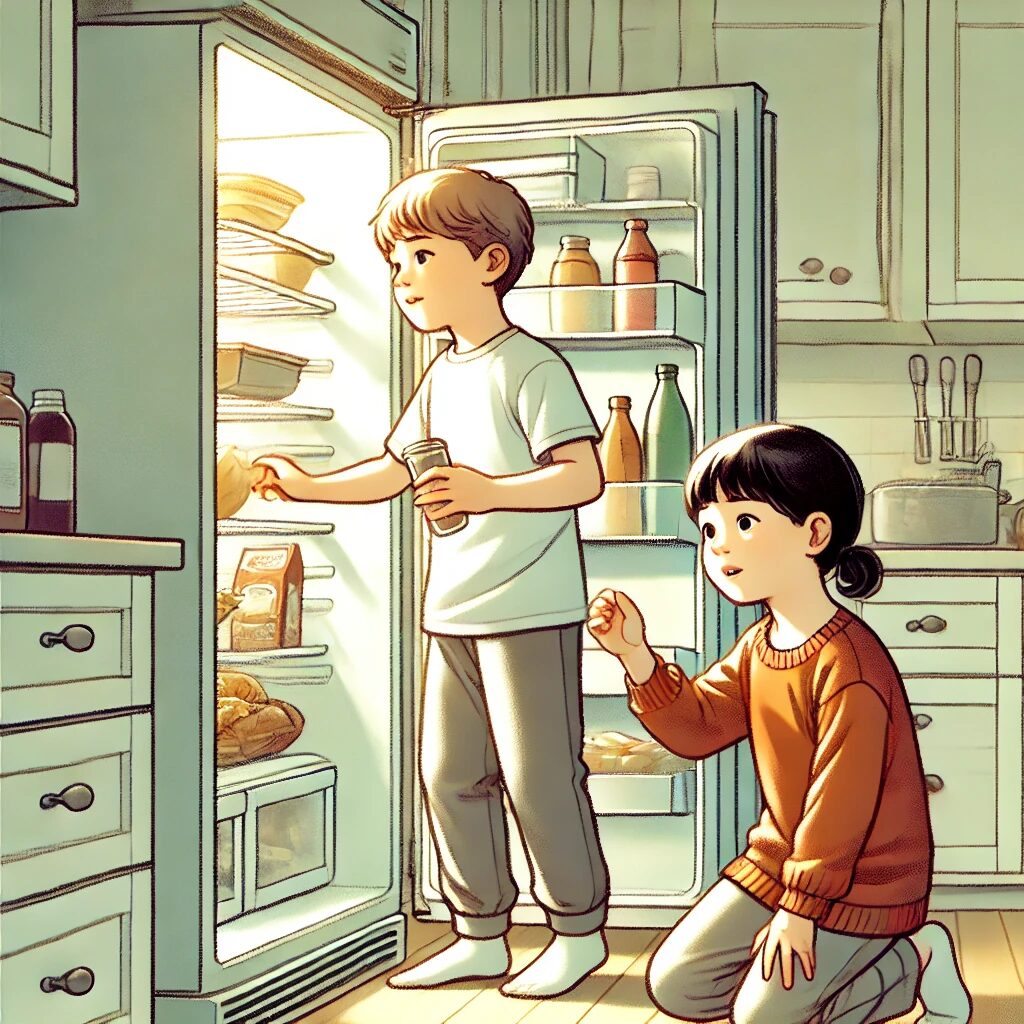
長期間マルトリートメントを受け続けたばあい、子どもの脳には以下のような変化が起こることがあります。
- 聴覚野の変形 → 怒鳴り声や暴言などの影響で、音に過敏になりやすくなる。
- 脳梁の縮小 → 左右の脳の情報伝達がスムーズにいかなくなり、感情コントロールが難しくなる。
- 前頭前野の縮小 → 自分の感情や行動を制御する力が弱まり、衝動的な行動を取りやすくなる。
- 視覚野の縮小 → 環境からの情報処理がうまくできず、不安や恐怖を感じやすくなる。
子どもたちの変形した脳は「ただ怖がりなだけ」ではありません。
それは 必死に生き延びようとしている証です。聞きたくない、見たくないものが多くて苦しくても、子どもなりに懸命に状況に適応しようと頑張ってきた証拠です。
でもそれは『傷ついてきた悲しい証』でもあります。
マルトリートメントを防ぐために

マルトリートメントは 気づかないうちに行われている ことも多く、大人が意識して避けることが大切です。
- 子どもの「小さなSOS」に気づくこと
→ いつも怯えている・落ち着きがない・自己否定的な発言が多いなどの変化が見られる場合は要注意です。子どもが内心嫌がっているのに異性の親とお風呂に入れることや、お風呂上りの親がいつまでも半裸や全裸で家の中をうろうろとすることもできれば避けてください。 - 親自身のストレスを適切にケアすること
→ 育児のストレスを感じたら、一人で抱え込まず、相談できる相手を探してください。直接的な問題解決にはならなくても「わかってくれる人がいること」がストレスを軽くすることがあります。 - 周囲のサポートを活用すること
→ 子育て支援センターやカウンセリングなど、専門機関を利用し、親と子ども両者にとって良い環境を作るための支援は遠慮なく活用してください。支援は積極的に手を挙げた人から受けられます(今の日本はそんな感じよ…ごめんね💦)だから、手を挙げて助けを求めてください。声を上げてください。
我々大人が、親が――マルトリートメントを減らし、安心できる環境を作ることが、わが子の未来を守る第一歩になります。まずは子どもの示す小さなSOSに気づき、声にならないHELPを見過ごさないこと。そして、親も同じく手を挙げて必要なら支援をもとめてください。わずかな遠慮さえも不要です。










