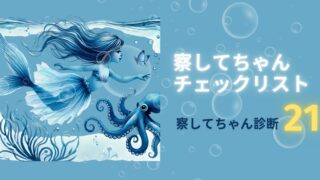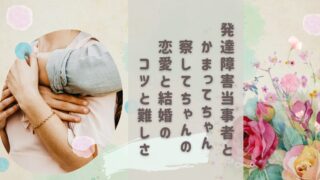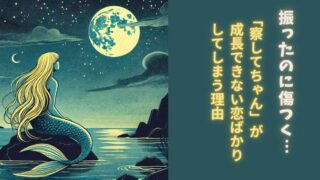共感力が「ない」って具体的にどういうこと?
共感力が「ない」というのは、一般的には「他者の感情や視点を想像したり、理解したりすることが難しい、もしくはそういった行動を取ろうとしない状態」を指します。
もう少し具体的に言うと、以下のような特徴や行動が見られることが多いです。
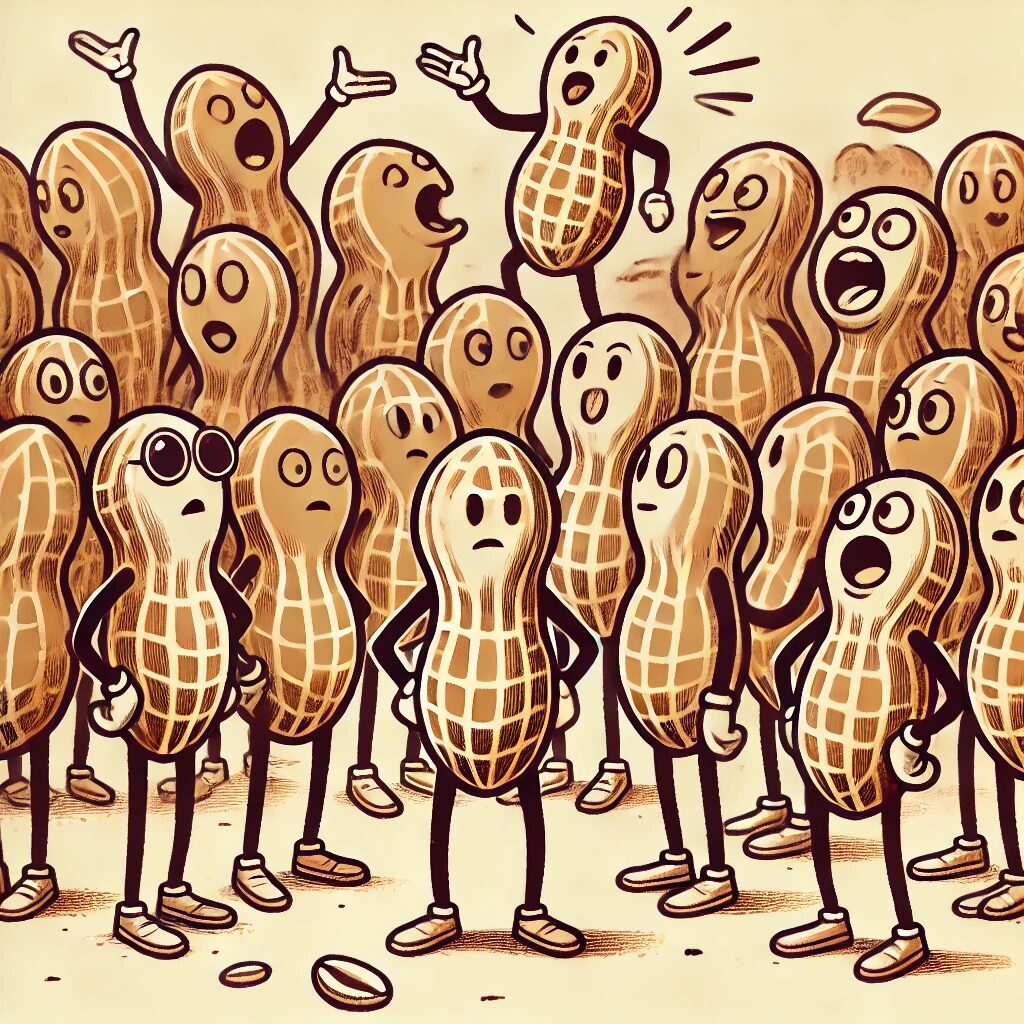
1. 他者の感情や状況を想像しにくい
- 相手が悲しんでいたり困っていたりしても、その理由や感情の動きを想像するのが難しく、適切な対応をとれないことがある
- 会話や相手の表情・声色・仕草などから感情を読み取るのが苦手で、言外のニュアンスを理解しにくい
2.自分の基準や価値観を強く押し出しがち
- 自分の考えや感じ方を基準にして「こうすべき」「こう考えるべき」と伝えてしまい、結果として相手の立場や感情への配慮が不足しているように見える
- 相手の気持ちや状況を考えるハードルが高く、自分の都合や自分の過去の成功体験から判断したり行動してしまうことがある
3. 相手の感情への関心や反応が薄いように感じられる
- 誰かが喜んでいても、同じテンションで共に喜ぶことが難しい
- 人が辛そうにしていても「大変そうだな」とは思うものの、具体的に手を差し伸べる「タイミング」や「方法」「かける声や適切なメッセージ」を思いつくことが難しい
- 「相手の痛みを想像して苦しくなる」という感覚が少なく、感情的に動かされにくい
4. コミュニケーション上のトラブルが起こりやすい
- 自分の言動が、相手を傷つけていることに気づくことが難しく、適した謝罪や適切なフォローにハードルがある
- 結果として誤解や衝突につながることがあり、対人関係でトラブルを引き起こしやすい
- 周囲の空気や場の雰囲気を読み取るのが苦手で、結果としてマナー違反のように受け止められることもある
5. 行動が自己中心的に見える(またはそうとられやすい)
- 相手の都合や感情よりも、自分の欲求や利益を優先しているように映る場合がある
- 周囲が「困っている人を助けて」と声をかけても、どのように行動すればよいかわからず、積極的には動きづらい
なぜ共感力が「低い」状態になるのか

–生まれつきの気質や発達特性
たとえば自閉スペクトラム症(ASD)など、社会的コミュニケーションや相手の感情を読み取るのが難しい場合がある
※ただし、ASDの方すべてが「共感力がない」わけではなく、共感の示し方や伝え方が独特な場合も多々あります。
–育った環境
幼少期から他者の感情や立場を考える機会が少なかった場合や、共感や助け合いよりも競争や個人主義が重視される環境で育った場合など
–トラウマや心理的防衛
過去の傷ついた経験から、他人と深く関わることを避けるうちに、自分から共感を閉ざしてしまうケースもある
–精神的・心理的状態
ストレスやうつなどで自分自身の心の余裕がなく、他者へ意識を向けるエネルギーをもてないことがある
「共感力がない」と言われる人への理解・アプローチ
- 悪気があるわけではなく、単に共感の仕方を学ぶ機会が少なかっただけという場合も十分に考えられる
- 心理カウンセリングや訓練的アプローチ(ソーシャルスキルトレーニング等)によって、「気づき方」や「リアクションのとり方」を学ぶことで変化が期待できる
- 周囲のサポートや環境調整によって、コミュニケーションがスムーズになる場合もある
「共感力がない」ことは「悪」ではない
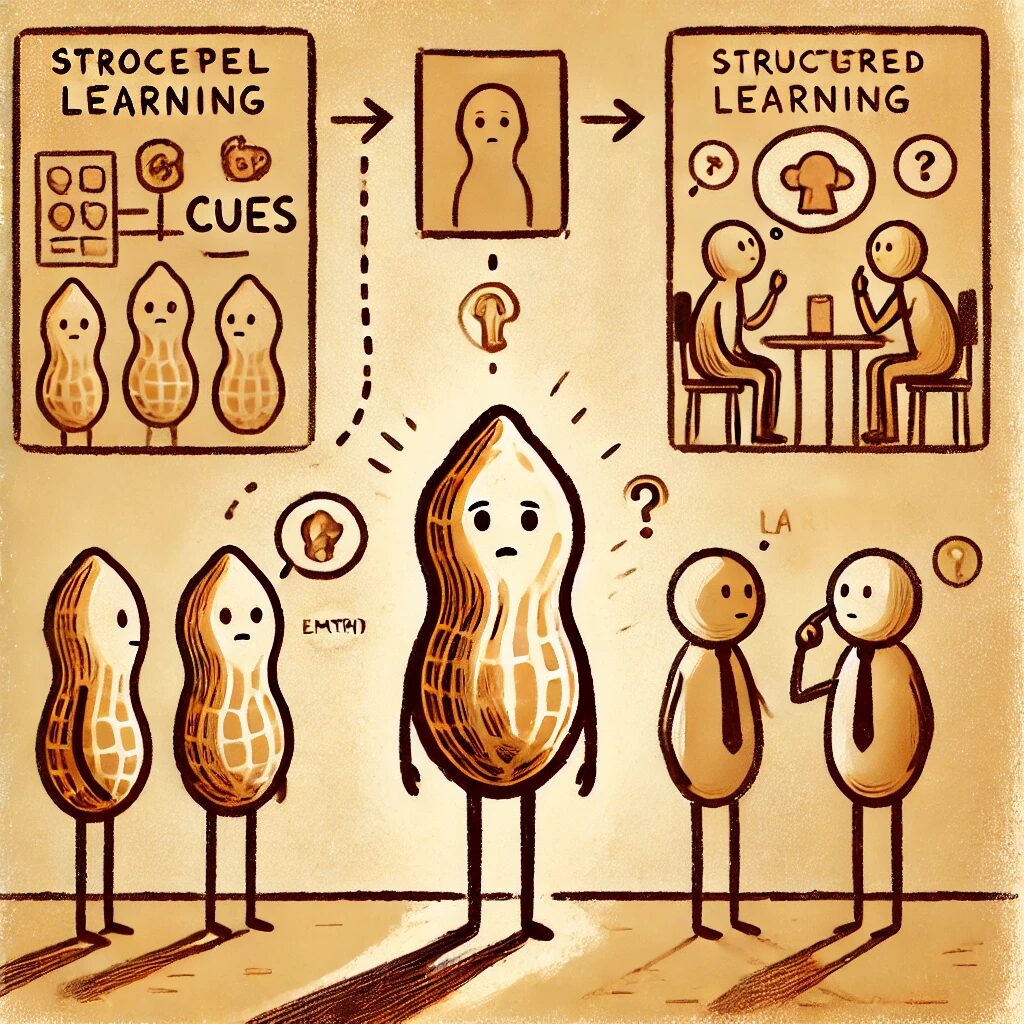
「共感力が低い」「共感力がない」と表現される状態は、他人の感情に気づきにくく、それを理解・共有する行動や姿勢を取りづらい状態を指します。共感力の低いもしくは少ない人たちが、「冷酷」であったり「他人を傷つけたいわけでは決してない」ということが、正しく広まればと願ってやみません。
発達特性や特異な家庭環境などにより、他者の感情を敏感に察知して、臨機応変に対応する力にハードルの高さがあるばあいや、経験が少ないケース。現在置かれている状況から「自分のことで手一杯」なばあいなど、さまざまな背景や理由が考えられます。
本人の性格・発達特性・育成環境など複合的な要因によって「共感しづらい」状態が形成されていることが多いため、一概に断罪するのではなく、背景や要因を知ってほしいです。