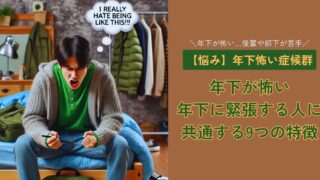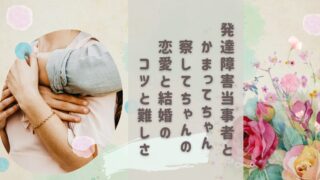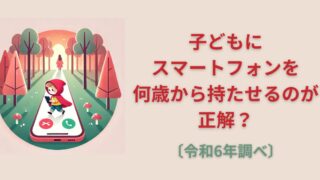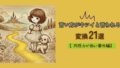前回のコラムでは「悪意や問題のない」、健全な成長過程を辿っているとも言えるウソを吐く思春期の心理についてまとめました。
「成長の通過点としてのウソ」とは異なり、今回のテーマは深刻性をはらんだケースを中心に扱います。同じウソでも、その背景や意図によっては大きなトラブルに発展したり、本人の将来に影響を及ぼすリスクがあります。
「問題のあるウソ」とは?

他者を傷つける意図がある
思春期のウソの中でも、「相手を陥れたい」「相手を傷つけたい」「誰かを困らせたい」というはっきりとした意図のあるケースがあります。
たとえば、いじめや誹謗中傷、意図的に誤った情報を広める行為などは、相手の心や名誉を深く傷つけることにつながるため、大きな問題です。こうしたウソには攻撃的な側面が含まれるため、事態が悪化する前に保護や学校側などの大人が早めに声をかけたり、対応したりすることが大切です。
例えばこんなケースが考えられます
- 根拠のない噂話を学校やSNSで広める
──「あの子がこんな悪いことをしていた」と事実と違う内容を周囲に流し、相手を孤立させる。 - わざと誤解されるような言葉や表現を使う
──「○○ちゃんが悪口を言っていた」と大げさに言いふらして、友人関係を乱そうとする。 - 被害者を装って同情を集める
──実際には嫌がらせを受けていないのに、「いじめられている」と周囲に嘘をつき、他人を悪者に仕立てあげる。 - 大事な物を隠す・壊すなどの行為を否定する
──「私じゃないよ」「俺は知らない」と言い張って相手に責任をなすりつけ、混乱を招く。 - 先生や親に「相手が悪い」と報告する
──自分の非を隠すため、あえて相手を悪者として話を作り上げることで、周囲の評価を下げようとする。
こうした行為は本人には「とっさの自己防衛」や「周囲を巻き込みたい」という思いがあるかもしれませんが、被害にあう側からすると深刻なダメージを受けること必至です。
このウソが危険な理由

このタイプのウソの怖いところは、「ウソでうまくいった」「ウソで思い通りに事が運んだ」という成功体験を1度でも得ると、それが習慣化し、大人になってからも使い続けてしまう可能性が高い点です。
とくに、相手を悪者に仕立てたり、相手が言ってもいないことを大きく言いふらしたりする「陥れるようなウソ」が繰り返されると、被害を受けた側は出社できなくなったり、不安障害を引き起こすほどのダメージを負うこともあります。
このタイプのウソをつく子は、早ければ小学生くらいからその傾向が見えはじめることがあります。たとえまだ幼い年齢であっても、何らかの理由で「相手を傷つけることを目的としたウソ」を選んでしまう背景には、いくつかの心理的・環境的な要因が考えられます。
考えられる要因
- 自分を守るための“攻撃的”な手段として身につけている
- 家庭環境で安心して本音を言える雰囲気が足りない
- 自尊感情(自己肯定感)の低さ
- 周囲の大人の対応や反応を見てウソを学習している
- 本人が抱える対人トラブルやストレスを解消できていない
親が知っておきたいポイント
- ウソの背後にある「助けて」のサインに気づく
「攻撃的なウソ」を選ぶ子どもの多くは、何かしらの理由でうまく気持ちを表現できないまま、心の中に葛藤やストレスをため込んでいることが少なくありません。
親としてはウソを一方的に責めるのではなく、「なんでこんなウソをつかなくちゃいけなかったのか?」と、気持ちや状況に目を向けることが大切です。 - 正直に話しても大丈夫と思える環境づくり
ふだんから自分から謝ったり本当のことを言えたりする雰囲気をつくってください。「怒るより先に事情を聞く」「話をしっかり最後まで聞いてあげる」だけでも、子どもの安心感は大きく変わってきます。 - 専門家や学校との連携も視野に入れる
ウソが常習化していたり、相手を深く傷つけてしまうような状況が続いているばあいは、一度スクールカウンセラーや地域の子ども相談機関に相談してみるのも手です。中立的な立場の大人に話を聞いてもらうことで、子どもの気持ちが整理されることがあります。

ウソにはいろいろな形があるものの、「相手を陥れたり、孤立させたり、傷つけることを目的にしたウソ」は相手にとってはダメージがあまりに大きく、子ども本人にとってもリスクが大きい行為です。幼い段階で早めに傾向を見つけ、子どもが抱えている葛藤や不安を少しずつ解きほぐすことで、深刻なトラブルを予防することができます。
こういったケースのウソが子どもや大人に見られると昨今ではなにかと「サイコパス」「ソシオパス(反社会性パーソナリティ障害)」と語られることが多いきらいがありますが、一般的な有病率は2〜3%です。
ですので、そういった障害としてではなく、誰かを陥れて自分の立場を守るようなウソをわが子がついているという事実への対処が必要だと私は考えます。つづく