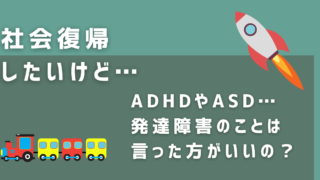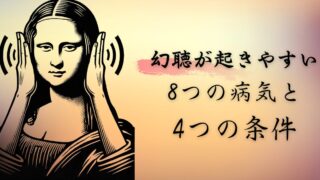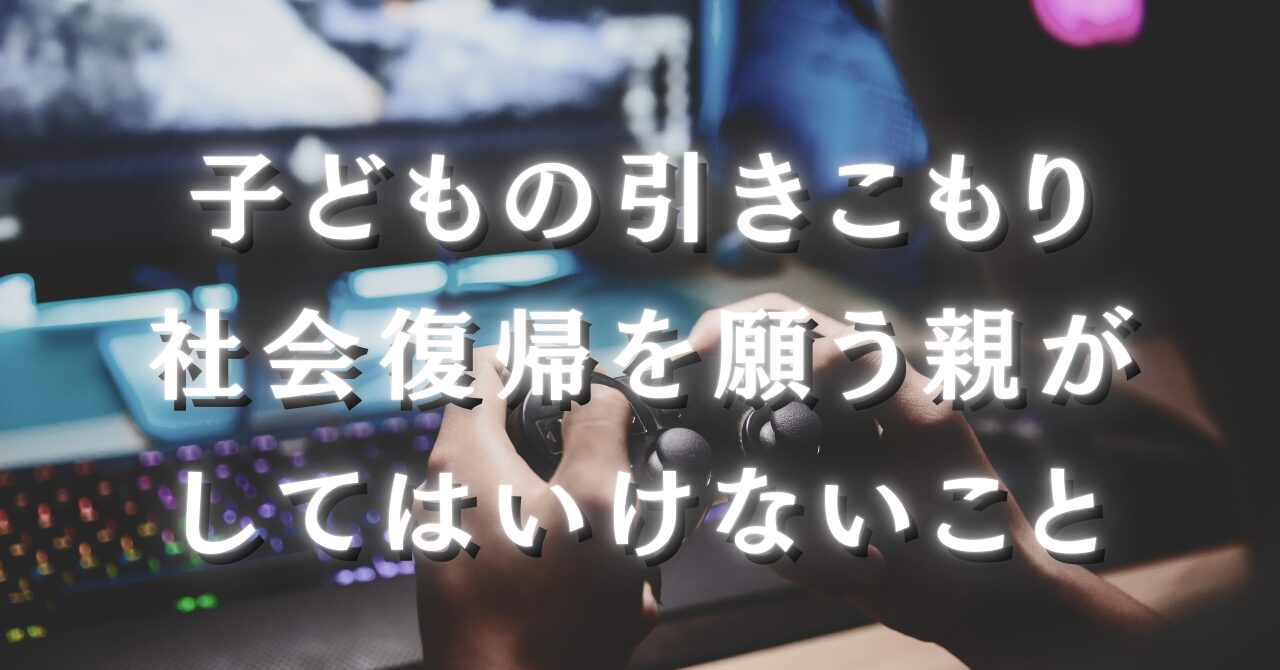「もういい加減に働きに出なさい!」「いつまで家にいるつもり?」
そう言いたくなる気持ちは、とてもよくわかります。親としては、一日でも早くわが子が元気に働き、笑顔で外の世界へ踏み出せるようになってほしいのですから。
でも、親が子どもを「1日も早く社会復帰させたい…!」と思うならば、避けたほうがいい言動があります。子どもとの関係が悪化してしまうだけでなく、本人の意欲や体調を損ねてしまい、かえって「復帰の道のり」を長引かせることにもなりかねません。
ここでは、息子さんや娘さんの引きこもりに悩むあまりに、私と同世代(50代~60代前後)のお母さんやお父さんがついやってしまいがちな言動を中心に、注意したいポイントをまとめました。
1. 決めつける・断定する
具体例
- 「何も考えずにダラダラと怠けているだけ」
- 「あれ嫌これ嫌、仕事を選り好みしてるんだろう」
こうした言葉は、一時のいらだちから出てしまいがちですが、本人を追い詰める要因になります。
表面上はぼんやりしているように見えても、本人の内側には「将来への不安」「過去の人間関係のストレス」など、さまざまな思いが渦巻いているものです。
「どうして皆みたいに動けないんだろう」と自分でも答えを探している最中に、親から「怠けている」と決めつけられたら、ますます自分を責めるか、心を閉ざしてしまいます。
「怠けている」ように見えても、実はうつ状態やその他の不調で動けない・働きたくても働けない場合もあります。いちばん大変なのは「自室から出てこられなくなること」です。
自室から出てリビングで過ごしたり、ダイニングで食事を摂ったり、たまに外に出て買い物をしている様子が見られるのであれば、大丈夫です。挨拶や日常会話をふつうに交わしてください。そこに嫌味や尖ったモノの言い方は必要ないです。
あなたのお子さんを信じてください✨
2. 他人と比較する
具体例
- 「同じ年の○○ちゃんはもう立派に働いてるのに」
- 「あなたのいとこは結婚もして子育てもしているわよ」
「比べても仕方がない」とわかっていても、つい口をついて出てしまうことがあるかもしれません。
しかし、「誰々と比べられた」という事実は、本人にとって大きなダメージになります。
「自分には価値がない」「情けない」――そんな思いを強めるばかりで、前向きな気持ちにはつながりません。
どう考える?
- 周りが急かしたり、他人と比較したりするほど、本人は「どうせ自分なんて」と気力を失っていく可能性があります。
- 他人は他人、わが子はわが子。短距離走が得意な子がいれば、ラストスパートで追い上げることが得意な子もいます。
3. 無理やり外に連れ出そうとする・急かす
具体例
- 「毎日家にいてもしょうがないから、就職説明会に行きなさい」
- 「バイトでもなんでも探して、応募してみればいいじゃない!」
外に出られないのは、一時的に心が疲れている、あるいは対人恐怖が強くなっているなど、何かしら理由がある場合が多いです。
無理に連れ出されたり、急に「働き口を探せ」と言われても、心の準備ができていないとストレスばかりが募ります。
結果として、本人は「外は怖い」「もう親に話すのはやめよう」とさらに閉じこもってしまうかもしれません。
どうサポートする?
- 「外に出たい気持ちが少しわいてきたら、声をかけてね」など、本人の意志を尊重するような言葉がけを心がけましょう。「買い物に付き合って」と親の用事に付き合ってもらうくらいのところから始めてみるのも良いでしょう。
- 状況に応じて、カウンセリングや専門の支援機関を利用するのも一つの方法です。
4. 親だけで問題を抱え込む・引きずり回す
具体例
- 親の独断で医療機関や支援施設の予定をどんどん取り付け、本人を連れまわす
- 親が「私が何とかしなくては」と焦ってしまう
お子さんが社会復帰できない状況が続くと、親としては「自分がもっと頑張れば、なんとかできるのでは」と思い詰めてしまうことがあるかもしれません。
しかし、無理やり外部の機関に連れて行く、あるいは親だけで必死になりすぎると、本人の気持ちが置き去りになる恐れがあります。
バランスを取るには?
- 情報収集は大切ですが、本人と相談しながら選択肢を見せる、同意を得て進むことが大事です。
- 親自身が疲弊してしまうと、本人を支えるどころではなくなります。親の心のケアや、親にとって相談しやすい相手を見つけることも必要です。
5. お小遣いの押しつけ・厄介払い
具体例
- 「お小遣いをあげるから、外に行きなさいよ!」
- 「お小遣いを渡すから、美容室で髪だけでも綺麗にしてきて!」
これは私の弟が大昔、1年半ほど無職の期間があった時に母が彼に向ってよく言ってた台詞です。
母からすれば「外に出てほしい=少しでも社会に繋がっていてほしい」という気持ちと、「せめて見た目くらいは整えてほしい=世間体」という気持ちの両面から出た言葉だったのだろうと思うのですが、言葉のチョイスが悪いというのですかね… ※実際にはもっと酷いことも言っていました
邪魔者を追い払うような、厄介払いをするような物言いに、弟も周囲の私たちも嫌な気分になったものです。
代わりにどうすれば?
- 身なりに構わなくなるのは、鬱の初期症状。
- 構わなくなるというより「構う気力が失われていく」というのが正解です。
- 鬱の状態が悪化し、外に出たくても出られなくなる前に、メンタルクリニックやカウンセラーにお子さんを委ねるのも一つの提案です。
まとめ
「社会復帰をさせたい」と願うあまりに、
- 決めつけ・比較・急かし・過干渉や厄介払い
といった言動をしてしまうと、かえって逆効果になることが少なくありません。
もし、今、親御さん自身が「わが子を早く社会に出してあげなければ…!」と焦っていると感じたら、少し立ち止まってみてください。
子どもが動けない理由は何なのか、本当の気持ちはどこにあるのか、それを知るには「ゆっくり対話する時間」と同じだけ「信じて見守ること」も大切です。また、支援機関やカウンセリングを利用して、親自身がサポートを受けてもよいのです。
「社会復帰」は焦っても上手くいかないことがあります。
重複になりますが「自室にこもりきり」になると、あとあと大変です。
部屋から出てきて顔を合わせたり挨拶を交わしたりダイニングで食事を摂っているうちは、大丈夫です。どうか無理をせず、無理をさせず、親子ともに心と体を大切にしながら、少しずつ道を探してみてください。