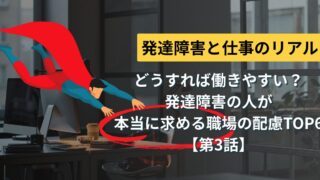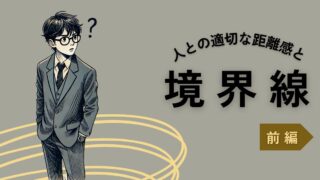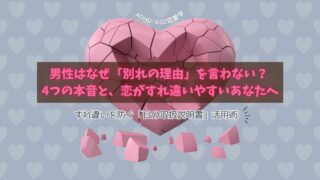「うちの職場にも、もしかしたら…」「自分自身のことかもしれない」。
近年、ASDやADHDやLDなど発達障害の特性を持つ方々の働き方、そして雇い入れた側の企業の理解の不足についてしばしば議論に上がります。
自身の持つ特性と従来の職場環境が合わず、知らず知らずのうちに「見えない壁」に直面し、苦労されている方が少なくありません。
このコラムシリーズでは膨大な調査結果を基に、発達障害の特性をもつ方々が働く上で抱えるリアルな困難や、本当に求めている配慮について、数回に分けて詳しくお伝えしていきます。企業の方にも、当事者やご家族の方にも、共に働きやすい環境づくりのヒントが見つかることを祈って――。
はじめに – このコラムシリーズでお伝えしたいこと
このコラムは、発達障害――ASD/自閉スペクトラム症や、ADHD/注意欠如・多動症、LDなど――の特性を持つ方々が、企業で働く(障害者枠雇用、一般雇用問わず)上で直面する困難や、職場に求める配慮をまとめた、まさに「リアルレポート」です。
「発達障害」「ADHD」という言葉は知っていても、具体的にどんなことで困り、どんなサポートがあれば力を発揮しやすくなるのか、イメージが湧きにくい方もいらっしゃるかもしれません。
このシリーズでは、日本における18歳から35歳前後の発達障害のある就労者の方々の声や調査データを基に、彼らが職場で抱える課題と、会社や上司に求めている具体的な配慮・支援策を、分かりやすく解説していきます。
企業側が明日から実践できる支援策のヒントとして、また当事者の方がご自身の状況を整理し、必要なサポートを考えるための一助となれば幸いです。
増えている? 発達障害のある若手社員の現状
近年、ASDやADHDなどに代表される発達障害の特性を持つ若者が、増えているというデータがあります。これは、発達障害への社会的な認知が広がり、診断を受ける人が増えたことや、企業側の障害者雇用への意識の高まりなどが背景にあると考えられます。
しかし、人数が増えている一方で、彼らの持つ特性と従来の職場環境との間にミスマッチが生じ、働き続ける上で様々な困難を感じているケースも少なくありません。実際に、多くの当事者が「仕事がうまくいかない」「人間関係が難しい」といった悩みを抱えていることが、調査やアンケートから明らかになっています。
なぜ今、この情報が大切なのか?
発達障害の特性のある方が職場で直面する困難や求める配慮について理解を深めることは、企業側にとっても、当事者側にとっても、そして社会全体にとっても非常に重要です。
- 企業にとっては…
- 多様な人材の能力を最大限に活かすことができる
- 社員の定着率向上、離職リスクの低減につながる
- 誰もが働きやすい、より良い職場環境づくりが進む
- 新たな視点や発想を得られる可能性がある
- 当事者やご家族にとっては…
- 自分の特性を理解し、困難の原因が分かり安心できる
- 必要な配慮を具体的に伝えやすくなる
- 能力を発揮し、やりがいを持って働ける可能性が広がる
- 孤立感を減らし、サポートを得やすくなる
つまり、発達障害のある方への理解と適切な配慮は、特別な誰かのためだけではなく、職場全体、ひいては社会全体の豊かさにつながる投資と言えるのです。
「見えない壁」の正体とは?
発達障害の特性を持つ方が職場で感じる困難は、しばしば「見えない壁」と表現されます。例えば、
「みんなが普通にやっていることが、なぜか自分には難しい」
「何度注意されても、同じようなミスを繰り返してしまう」
「職場の雑談の輪に入れない、話が噛み合わない気がする」
といった経験です。
これらの困難は、本人の「努力不足」や「やる気がない」といった性格の問題ではなく、発達障害のそれぞれの特性に起因している場合が多くあります。例えば、言葉を文字通りに受け取りやすかったり、一度に多くの情報を処理するのが苦手だったり、特定の音や光に過敏だったりする、といった特性です。
この「見えない壁」の具体的な内容については、次回のコラムで詳しく掘り下げていきます。
まとめ
第1話では、このコラムシリーズの目的と、発達障害の特性を持つ就労者の現状、そしてなぜ今この情報が大切なのかについてお伝えしました。
職場には、まだ気づかれていない「見えない壁」が存在し、それが働きにくさの原因になっていることがあります。このシリーズを通じて、その壁の正体と『就労者側・雇い主側の双方』が、乗り越えるための具体的なヒントを一緒に見つけていきましょう。
次回は、発達障害の特性のある方が職場で共通して抱えやすい「困難」について、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。
✍オンラインカウンセリング「あたらしい今日」主宰・カウンセラー真由
情報ソース