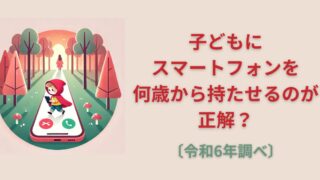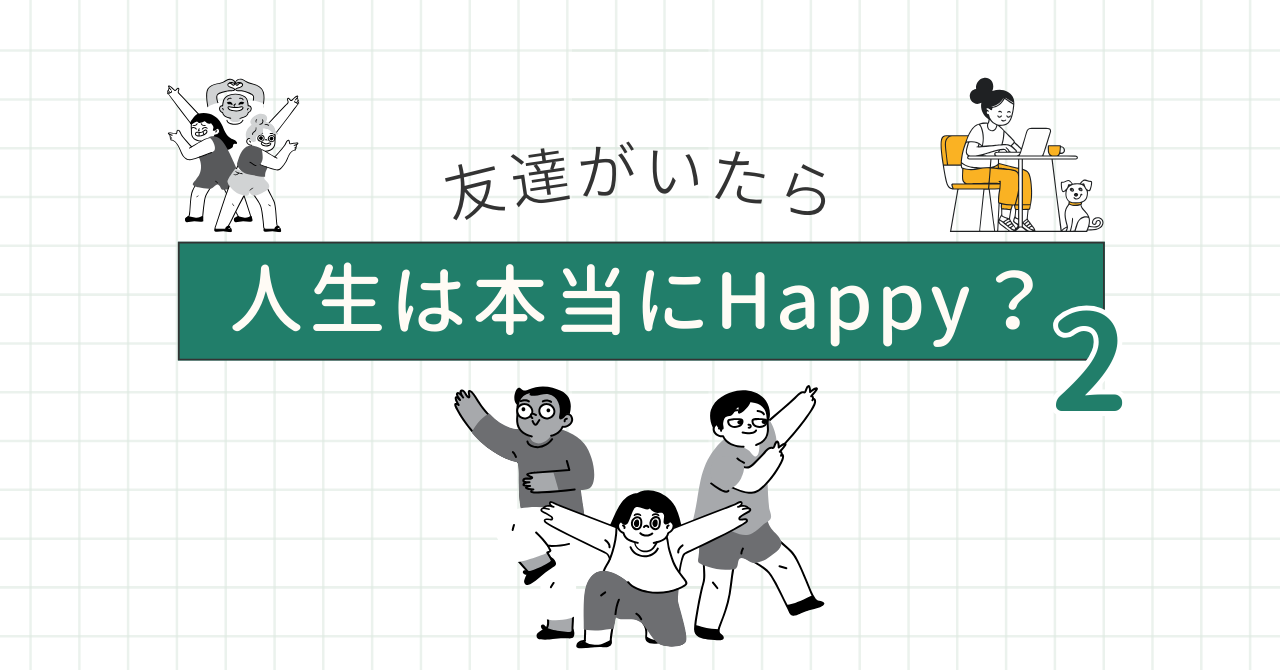ひとりが楽な子ども達──「友達ができない」と悩むママの心配
前回のコラムでは、「友達がいなくても必ずしも問題ではない」「人によってはひとりが楽だと感じるケースもある」という視点から、私自身の『友達をとくに必要としていなかった11歳~15歳』の頃の話題にも触れました。
「ひとりでいる=さみしい」とは限らないこと、友達がいない自分を親や周囲が心配しているということがプレッシャーになっていることもあります。
今回は、実際に「ひとりが心地いい」と感じる子どもたちのタイプを少し掘り下げながら、「うちの子に友達ができなくて心配…」というママがどんな風にサポートしたらいいかを考えてみたいと思います。
1.コロナ禍以降の友達の距離感
- 面と向かって話すのはちょっと苦手だけれど、SNSやゲームなどのオンラインを通してなら気軽に話せる。
- 物理的な距離があるぶん、ほどよい安心感をもってやり取りできる。
コロナ禍を経て「友達との距離感」はかなり変わりました。ネットでのやり取りは親世代には「薄い関係」と見えがちかもしれませんが、子どもたちにとってはすでに当たり前のコミュニケーション手段になっています。
2.「うちの子、友達ができない…」と悩んだ時に考えてほしいこと
まずは「本当に友達を欲しがっていないのか、欲しいけれどつくれないのか」を見極めることが大事です。
たとえば、
- そもそも“友達が要らない”タイプなのか
- “友達は欲しいけれど、どうやって接すればいいか分からない”タイプなのか
- “うまく友達ができても、何かの理由で離れてしまう”タイプなのか
タイプによって、アプローチの仕方は少しずつ違ってきます。
▷「友達がいなくても平気」な子への向き合い方
もしお子さん自身が「あまり友達を欲していない」と感じられるなら、まずはその個性を尊重してさしあげるといいと思います。ムリにグループに入れようとしたり、「たくさん友達を作りなさい」と急かしたりすると、逆にストレスになることも。
▷「本当は欲しいけど作れない…」という子のサポート
- 挨拶や自己紹介の練習を親子でやってみる
- ちょっとしたコミュニケーションのコツを教える
- 「はじめまして」の質問のあれこれ
- 急に相手に触ったり、相手が手に持っているものを奪ってはいけない
- 公共の遊具を使う時は「順番に」「ひとり占めしてはいけない」
- 習い事や地域のイベントを活用して、同年代のお友達と自然に関われる場所に連れ出してみる
少しずつ「人と関わるって思ったより楽しいかも」と思えれば、友達づくりのハードルが下がっていくことは多いです。
▷「せっかく友達ができても離れてしまう…」ときは
- 子ども本人の言動に原因がないか探ってみる(つい自己主張が強くなりすぎる、など)
- 周囲の環境やお友達との相性に問題がある場合もある
- お子さんが「どうしてうまくいかないんだろう」と悩んでいる様子が見られたなら、親子でいっしょに解決策を考えてみる
友だち関係が長続きしない理由を一緒に見つけて、「次の友達にはこうしてみようか?」と気持ちを整理したり、友達づくりのステップを作ってさしあげると、お子さんもラクになるかもしれません。
3.「ひとりが好き」な子どもには、こんないい面もたくさん
「友達とつるんでわいわい」も素敵ですが、ひとりを好む子にもたくさんの良さがあります。
- 自分で時間を使う力がつく
- 一人遊びをするなかで、何をして過ごすか自分で選び取る力が自然に養われます。
- 想像力・創造力が高まる
- 空想の世界に没頭したり、独自のアイデアを生み出したりしやすい環境を楽しめます。
- 自己肯定感が育ちやすい
- 他人と比較せず、自分らしい満足できる時間を持てることで自己充実感が満たされます。
- 問題解決能力が身につく
- 一人遊び中に困ったことがあっても、自分で対処しようとする経験が増えるので、自然と解決力が鍛えられます。
- 人間関係に執着しすぎない
- 「ひとりでも大丈夫!」という土台があると、友達付き合いに振り回されにくくなり、情緒が安定します。
- 集中力や忍耐力が養われる
- 一人の世界を楽しむには、何かに没頭する時間が多くなるので、コツコツと取り組む習慣が育ちやすいです。
4.おわりに──「選択ぼっち」からのメッセージ
前回のコラムで少しお話ししましたが、私自身も子どもの頃から「ひとりが楽」というタイプでした。今時の言葉で言うと『選択ぼっち』ですね。
とはいえそんな私にも高校時代には何人かの親友ができて、大学や大学院では切磋琢磨する仲間も増えました。しかし、当時の親友たちといまだコンスタントに連絡をとりあっているかといえばそうではありません。
年に1~2回、近況報告がてらに季節の挨拶をしたり、バースデー祝いのLINEを送ったりLINEギフト経由でプレゼントを贈ったりといったシンプルな関係。
ふだん連絡を取り合うのは、30代に入ってからできた親友と、40代に入ってから仕事の繋がりで親しくなった友人の2人です。とはいえ彼女達にも家庭があり、私と同じく他人に依存したり他人に期待しないさっぱりした性格なので
「基本はひとりでいたいけど、2~3か月に1度、食事を楽しむような肩ひじ張らない付き合い」を求めるもの同士、楽な付き合いが続いています。
そうなんです。人間って不思議なもので、本来は『似たようなタイプと仲良くなる』んだと思います。一見すると真逆に見える2人にも、根底に流れている信念や道義みたいなものが似通っていたり。
そういう友達と適度な距離感を保ちながら、長いお付き合いを続けられていることが、人生の楽しみのひとつです。もしもあの頃…11歳から15歳当時…周囲の目を気にして自分の本心にウソを吐きながら「表面上のお友達」としたくもない付き合いをしていたら、きっと、今の私はいなかったと思います。
人の顔色ばかり見て、目立たぬよう出過ぎぬよう横一線の付き合いに一喜一憂して、マウントをとったりとられたりしながら傷ついたり傷つけたり。いわゆる『女子同士のしんどい付き合い』にヘトヘトになっていただろうなって。
あの頃、『選択ぼっち』だった私は、自分の好きな世界に思う存分興じていました。その世界に理解を示し一緒に楽しんでくれる女子は周りにはいませんでした。少なからず私の目に見えている世界にはいなかったの。
- 深夜ラジオ
- ボクシングや格闘技
- New jack swing(80年代の洋楽のジャンル)
- Smooth Jazz(80年代のジャズのジャンル)
- 心理分析
- 秩序型犯罪・無秩序型犯罪の傾向分析
- 妄想 ※今でいう“引き寄せ術”
同世代の女の子達が、少女マンガや男性アイドル・隣のクラスの誰々君に夢中になっていたり、バレンタインデーや席替え(笑)に色めき立つ中、私はそういったことにまったく興味がありませんでした。冷めてるってよく言われてたなーそういえば。
30代で知り合った親友とは深夜ラジオきっかけで一気に仲が深まり、40代で知り合い仲良くなった友人とは心理分析や犯罪分析関係で知り合い、互いの家を行き来するほど仲良くなりました。
なにより…夫とは「ラジオ」「格闘技・大相撲」「音楽」と共通の趣味が多く、結婚した当初から今も変わらずそういったイベントに2人でよく参戦しています。
子どもを思うあまり、不安になってしまうママの気持ちはとてもよくわかります。でも、お子さんが自分らしい楽しみ方を選んでいるのであれば、それは素敵なことのように思います✨ お子さんが大切にしているお子さんならではの世界観の理解者は、まだ近くにはいないかもしれません。
けれど、必ずどこかに同じ思いの「未来の友人」「永く付き合える仲間」と繋がっています。だから心配ないです。むしろとっても喜ばしいことだと思います✨
もちろん、「本当は友達がほしいのに、なかなかできない…」という場合は、少しサポートや工夫が必要ですね。でもそうではないなら「友達って、本人が本当に必要になったときに自ずとできるもの」ですので、あまり心配しすぎずお子さんをやさしく見守ってさしあげてください。
それではまた。いつでもご相談ください🌱