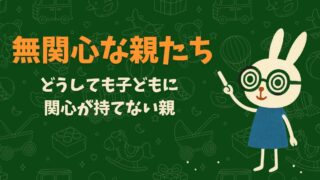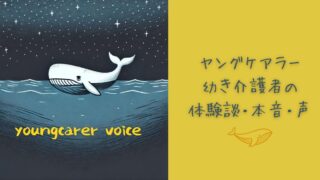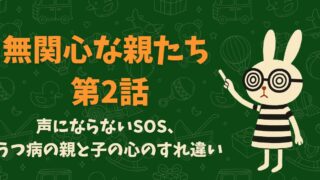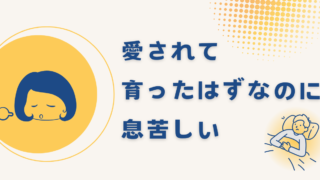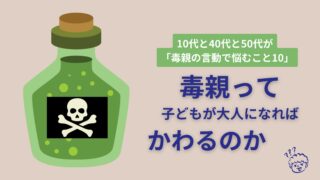心の距離、見えない壁 -「無関心」の仮面の裏側で、親と子が抱えるもの
「我が子に関心がない親」――この言葉を聞いて、あなたの心にはどんな風景が浮かびますか?
冷淡で、育児を放棄しているような親がイメージされ、どこか遠い世界の出来事のように感じるでしょうか。
無関心と言ってもその理由は実は一様ではなく、さまざまな背景が絡んでいます。
例えば、うつ病を抱える親は、どれだけ子どもを愛していても、その愛情を表現する余裕が『病気のために』ありません。気力やエネルギーが足りず、日々の育児に関心を持つことすら難しい場合があるのです。
また、発達障害のひとつである受動型ASDが特性としてあると、情緒的な感情の交流や子どもとの接し方に難しさを抱えていることがあり、子どもを愛している気持ちは十分にありながら、その思いを言葉や表情や態度に示すことがうまくいかないことがあります。
さらに、子育ての方法がわからないと感じる親や、面倒を避けたいという心理的な理由で無関心になってしまう親もいます。無意識のうちに、特定の子どもに対して冷たくなったり、疎遠になることもあります。
また、ある親は、子育てに対して過度な期待を持っている一方で、自分の個人的な欲求やアイデンティティを優先し、結果的に子どもを無視してしまうこともあります。
「無関心」の裏側には子ども自身が想像する以上に、親自身の痛みや葛藤、そして複雑な事情が隠されていることがあります。
しかし…親側の事情はともかく「親の無関心」は子どもにとって心の奥深くに、静かに、しかし確実に見えない影をあまりに長く落としていきます。
「無関心」に見える親の代表的な5つの例
- 受動型ASDなどの発達特性▶どう関わればいいのか、愛情の伝え方に戸惑い、もどかしさを抱えている親御さんもいます。
- うつ病などの心の不調▶「愛しているのに、応えられない」…そんな苦しみを抱え、気力もエネルギーも湧かず、ただ日々をやり過ごすので精一杯という状況も。
- 子育てへの不安や孤立▶誰にも頼れずどうしていいか分からず、途方に暮れているうちに、関わること自体が億劫になってしまう。
- 心理的な壁▶面倒事を避けたい、子どもという存在がそもそも苦手、あるいは特定の子にだけ、なぜか心が動かない…そんな言葉にしにくい感情。
- 親自身の心の傷や未熟さ▶自分自身の問題で手一杯で、親である前に「男」「女」でいたいという気持ちが勝ってしまう。
これらはほんの一例です。「無関心」の背景には、親自身の苦悩や、本人の意志だけではどうにもならない現実が横たわっていることも多いのです。それは決して他人事ではなく、私たちのすぐ隣にあるのかもしれません。
とても大切なのは、これらの親の無関心が必ずしも「子どもへの愛がない」ことを意味するわけではないということです。この点が問題をより複雑にしています。
なぜ愛してくれなかったの?
親からの関心の欠如は子どもの柔らかい心に、言葉にならない寂しさや、不安を刻みつづけます。
- 「親がいつも忙しくて、気づいてくれることなんてなかった。でも、自分はそれが普通だと思っていたから、無理に愛を求めることもしなかった。親が頑張っているんだから、自分でやらなきゃいけないんだって思ってた」
- 「兄妹の中で、私が一番しっかりしていて手がかからないから放っておかれてると思ってた。寂しかったけど頼られてる証拠だと思って受けいれていた。でも違った。還暦を迎えた母から『あんたとはずっと性格が合わなかった』と言われて愕然とした」
- 「父親がうつ病だと気づくのが遅かった。家の中は沈んだ空気が毎日漂っていて、それが全てだと思ってた。愛情を表現することができない父の無関心が、私にはどれほど辛かったか、成人してからようやく理解できた」
子どもに関心が持てなかった親達とその子ども達の物語、はじまり
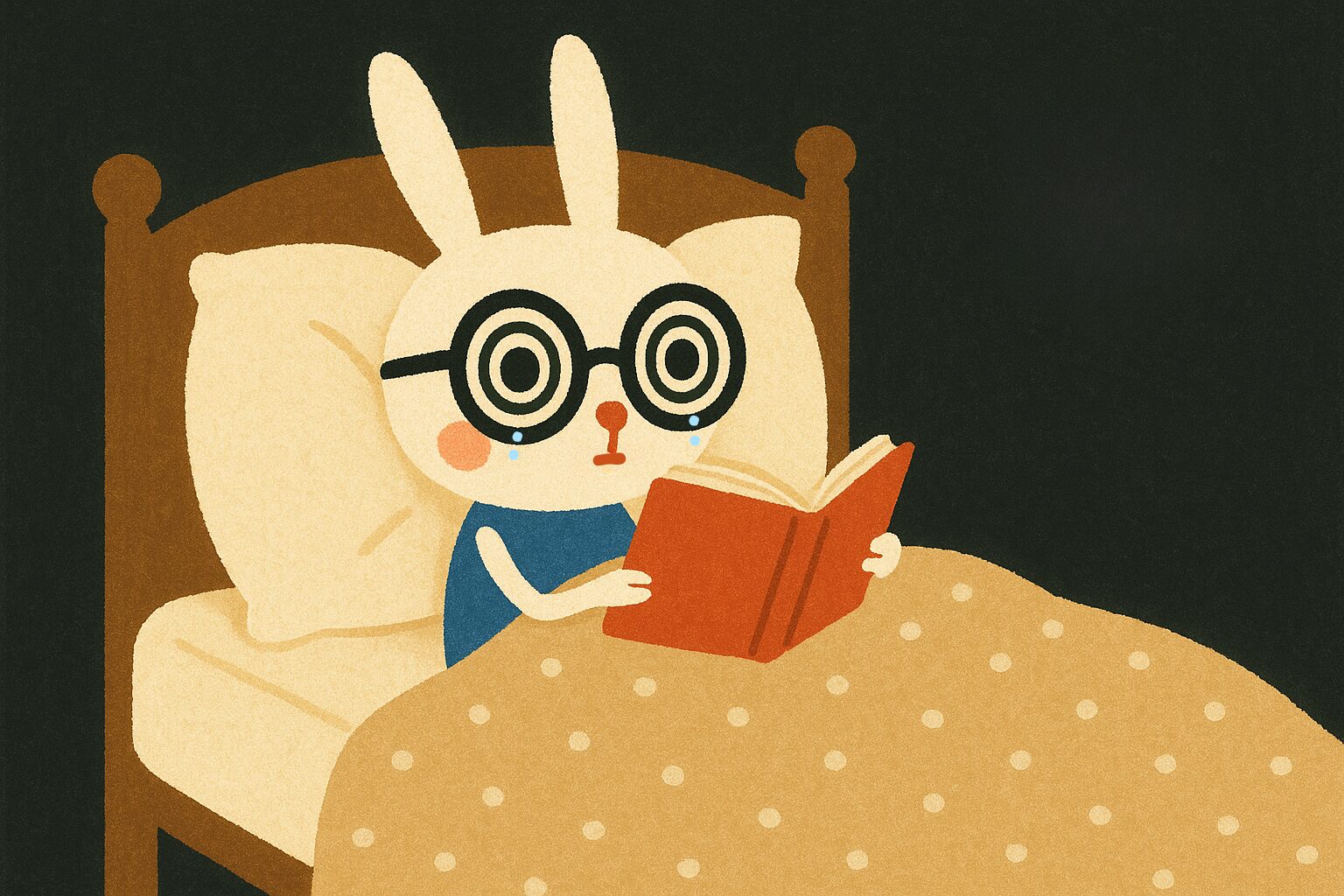
無関心な親に育てられた子どもたちは、愛されていないわけではないということを理解しつつも、何かが欠けていることをその繊細な心で感じ取っていたのです。
その「何か」を自分なりに埋め合わせようとしてきた子どもたちが大人になったとき、無関心の影響がどのように残るのか、今後の人生にどれほど色濃く影響を与えるのか、心を寄せて見つめていきたいと思っています。
今後「無関心な親たち」というテーマで数回に分けてコラムを書いてまいります。「無関心な親たち」の多様な背景と、寂しさと自己解釈のはざまでつらい思いをしてきた子ども達にとってわずかにも救いになれたらと願いながら――。
✍オンラインカウンセリング「あたらしい今日」主宰・カウンセラー真由