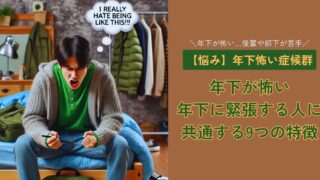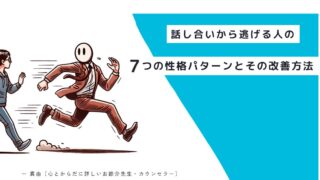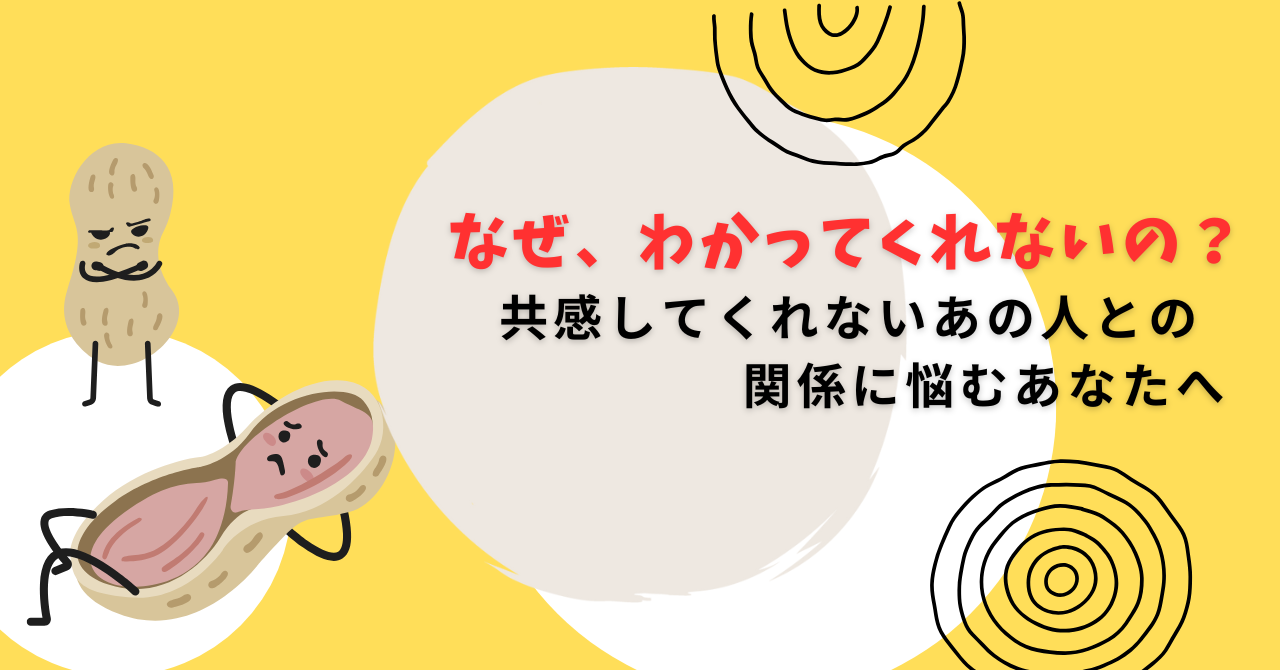「どうしてもっと共感してくれないの?」知ってほしい、その背景にあるもの
特定の誰かに「どうしてもっと優しい言葉で言えないんだろう?」「どうしてもっと分かろうとしてくれないんだろう?」と感じてしまったことはありますか?
相手の胸の痛みや、立場の弱い人の気持ちをわかろうとしていないように見えたり、言葉にうまくできないモヤモヤを分かってくれないように感じたり、ちょっと自分中心に見えたり、「確かにそうだけど…」と言いたくなるような正論を振りかざされたり…。
そんな時、私たちはつい「この人って冷たい人なのかな」と思ってしまうかもしれません。でも、その背景には私たちが知らない様々な事情が隠れていることがあります。この記事では、「共感するのが苦手」に見える人たちの心の働きについて、様々な視点から理解を深めていくヒントを届けます。
「共感するのが苦手」ってどういうこと?
「共感力が低い」「共感するのが苦手」「共感してくれない」とは一般的にどういう意味で使われているのでしょうか?
恐らくそれは「他の人の気持ちや考えを想像したり、それに寄り添ったりするのが難しい状態」を指すことが多いかと思います。具体的には、次のような様子が見られるかもしれません。
1.相手の気持ちを想像するのが、少し苦手 続きを読む
⦁ 誰かが悲しんでいたり困っていたりしても、その背景にある気持ちを想像するのが難しく、どう反応したら良いか戸惑ってしまうことがあります。
⦁ 会話の中で、言葉そのものだけでなく、表情や声のトーンに含まれる「なんとなく」のニュアンスを掴むのに時間がかかることがあります。
2.自分の感じ方や「普通」を基準に考えがち 続きを読む
⦁ 自分の経験や考え方をベースに「きっとこうだろう」「こうすべきだ」と話してしまうため、結果的に相手の状況や気持ちへの配慮が足りないように見えてしまうことがあります。
⦁ 相手の立場になって考えることに、少しエネルギーが必要で、自分の経験や「良かれ」と思って判断したり行動したりすることがあります。
3.相手の感情への反応が、少し分かりにくい 続きを読む
⦁ 誰かが喜んでいても、同じようなテンションで一緒に盛り上がるのが得意ではないかもしれません。
⦁ 人が辛そうにしているのを見て「大変そうだな」と感じても、具体的にどんな言葉をかけ、どう行動すれば相手の助けになるのか、すぐに思いつかないことがあります。
⦁ 「相手の痛みを想像して、自分のことのように苦しくなる」という感覚が、他の人よりは少ないかもしれません。
4.コミュニケーションで、すれ違いが起こりやすい 続きを読む
⦁ 自分の言ったことやしたことが、相手をどんな気持ちにさせているか、気づきにくい場合があります。そのため謝ったり、フォローしたりするタイミングや方法に迷うことがあります。
⦁ その場の雰囲気や「暗黙の了解」のようなものを読み取るのが難しく、意図せずマナー違反のように受け取られてしまうこともあります。
5.行動が、自分中心に「見えてしまう」ことがある 続きを読む
⦁ 相手の都合や気持ちよりも、自分のやりたいことや考えを優先しているように「周りの目には」映ってしまうことがあります。
⦁ 周りが「困っている人がいるから手伝ってあげて」と声をかけても、「具体的にどう動けばいいんだろう?」と戸惑い、すぐに行動に移せないことがあります。
どうして「共感するのが苦手」になることがあるの?
これには、本当に様々な背景が考えられます。一つだけが原因ということは少なく、いくつかの要因が組み合わさっていることも多いのです。
1.生まれ持った特性 続きを読む
⦁ 生まれつき、他者とのコミュニケーションの取り方や、感情の感じ取り方が個性的な場合があります。例えば、発達障害(ASDやADHDなど)の特性がある方の中には、相手の気持ちを読み取ったり、それに合わせた反応をしたりすることに、他の人とは違うプロセスや困難さを感じることがあります。
⦁ (大切なお断わり) ただし、これはあくまで一部の傾向であり、発達障害のある方すべてが「共感するのが苦手」というわけでは決してありません。共感の感じ方や表現の仕方が、周りの人とは少し違う、とてもユニークな形であることも多いのです。「共感力がない」と断定することは、大きな誤解につながります。
2.育ってきた環境の影響 続きを読む
⦁ 小さい頃から、相手の気持ちを考えたり、誰かと協力したりする機会が少なかった環境で育った場合、そうしたスキルを自然に身につけるのが難しかったのかもしれません。
3.過去の経験や、今の心の状態 続きを読む
⦁ 過去に深く傷ついた経験などから、無意識のうちに人と深く関わることを避け、自分の心を守るために感情にフタをしてしまうことがあります。
⦁ また、強いストレスや心の不調を抱えている時などは、誰だって自分のことで精一杯になり、他の人のことまで考える余裕がなくなってしまうものです。
「共感するのが苦手」な人への、優しいまなざし
もしあなたの周りに「共感するのが苦手かな?」「共感の仕方にちょっとクセがあるのかも?」と感じる人がいたら、少しだけ想像してみてください。
その人には、決して悪気があるわけではなく、ただ、共感の「仕方」を学ぶ機会が少なかったのかもしれないし、他の人とは違う感じ方をしているだけなのかもしれません。
- 人との関わり方を学ぶ(例えば、ソーシャルスキルを学ぶような場)ことで、コミュニケーションがスムーズになることもあります。
- 周りの人が少し理解を示したり、コミュニケーションの方法をちょっと工夫したりするだけで、お互いの関係性がぐっと良くなることもあります。「こうしてくれると分かりやすいな」と具体的に伝えてみるのも一つの方法です。
- 「共感するのが苦手」というのは、その人の一部分ではあっても、「悪いこと」ではありません。
さいごに伝えたいこと

「共感力が低い」「共感するのが苦手」と表現される状態は、他の人の気持ちに気づきにくかったり、それに寄り添う行動や姿勢をとるのが難しかったりする様子を指します。でも、その背景には生まれ持った特性、育った環境、過去の経験、今の心の状態など、本当に様々な理由が考えられます。
表面的な行動だけを見て「冷たい人」なのかも、「自分勝手な人」なのかもと思ってしまう前に、その裏にあるかもしれないその人なりの事情や背景に少しだけ思いを馳せて、お互いを理解しようと努めることがより温かい関係性を築く第一歩になるかもしれません。
だけど、もちろん、相手の背景を理解しようと努める一方で『今はただ、この気持ちに寄り添ってほしい』『ただ受けとめてほしい』と感じる瞬間があるのも、とても自然なことです。願いが叶うなら、その相手は「もっとも近いところにいるパートナーや親」であってほしいこともあるでしょう。
私自身も、かつてもっとも身近な人とのコミュニケーションにおいて、『気持ちを分かってほしい』と寂しさを感じていた時期が子どもの頃にありました。
当時はその理由が分からず、ただ辛い気持ちを抱えていました。
しかし心療内科領域を学びながら、カウンセラーとして様々な方と関わる中で、そして私自身が母となり年月を重ねる中で、少しずつ見方が変わってきました。
あの頃、私には厳しく、自分の正しさを譲らないように見えた母もまた、その態度の裏では、必死に誰かに理解され、無条件で受けとめてほしいと願っていたのかもしれない――そう思えるようになったのです。
このように共感をめぐる悩みは、時に深く、一人で抱えるには辛いものです。
もし、ご自身や大切な人との関係で、こうしたコミュニケーションの難しさを感じ、心が疲れてしまっているなら、専門家と一緒に気持ちを整理してみることも、状況を好転させるための一つの大切なステップです。
私・カウンセラー真由も、オンラインであなたのお話に誠実に耳を傾けさせていただきます。いつでも通話相談をご利用ください。
✍オンラインカウンセリング「あたらしい今日」主宰・カウンセラー真由